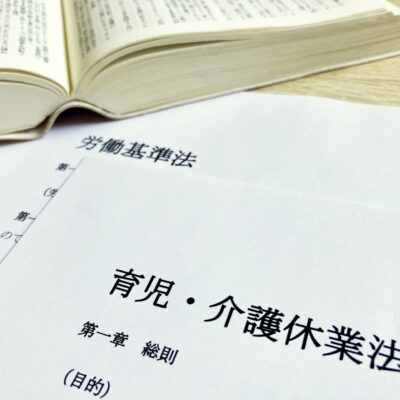【入門編】介護離職の定義と現状を知る!「介護離職しないための8ステップ+1」スタート
(お断り)
本稿は、2024年7月6日に当サイトで公開した記事を、一旦閉鎖し再開した当サイトに、本日再掲したものです。
当時の実態と現状では異なる内容が含まれていることがあり得ます。ご了承ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズー1
今回から、「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」というテーマでのシリーズを始めます。
現状予定しているシリーズ構成を最後に記しています。
9つの章で構成しますが、8つは介護離職をなんとかせずに家族介護に臨むことができるようにするための知識や準備について考える章。
最後の1つは、やむなく介護離職を食い止めることができなかった場合の対応について提起するものです。
それでは、第1章に入ります。
まず、シリーズの序論・序章に当たる、介護離職とはなにか、それが現状どういう状況にあり、今後どうなると予想されるか、根本的に理解・認識することを目的として進めます。
本記事に、広告を挿入することがあります。
第1章 介護離職とは? 介護離職の定義と現状を知ろう
1-1 介護離職の定義と現状
第1回第1項は、「介護離職の定義と現状」をテーマとして、以下基本事項を整理していきます。
1.介護離職の定義
介護離職の意味
介護離職とは、主に家庭内での介護負担が増大し、仕事と介護の両立が困難になることで、仕事を辞めざるを得なくなる状況を指します。
具体的には、家族や親族の介護が必要になった際、その介護に専念するために仕事を辞めることを意味します。
どのような状況で介護離職が発生するのか
介護離職は、以下のような厳しい状況で発生します。
・親や配偶者の介護が必要になったとき: 親や配偶者の介護を行う他の人がおらず、自分しか介護を担える人がいない場合
・突然の病気や事故で家族が要介護状態になった場合: 突然の事態により、家族が重度の要介護状態になり、在宅介護で24時間対応が必要となった場合
・長期的な介護が必要な状態が続く場合: 長期間にわたり介護が必要となり、介護者の肉体的・精神的負担が大きくなり、仕事と介護の両立が難しくなる場合
関連する用語とその意味
・介護者: 介護を行う人。家族や親族、場合によっては近隣住民や友人が該当します。
・被介護者: 介護を受ける人。主に高齢者や病気・障害を持つ人が該当します。
・介護負担: 介護者が感じる肉体的・精神的・経済的な負担を意味します。
・ビジネスケアラー: 仕事と介護の両立を試みる人。仕事を続けながら家族の介護を行っている人が該当し、介護離職に至るリスクが高いため、介護離職予備軍ともされています。
介護離職を防ぐためには、介護に関する知識を深め、介護の準備と計画を立てることが重要です。
介護サービスや地域の支援制度を積極的に利用し、家族や職場と協力しながら介護と仕事の両立を図ることが求められます。
これらの課題を、このシリーズでこれから取り上げていきます。
2.介護離職の現状
ここでは、3つの公的資料を用いて、介護離職の実態と推移について確認していきます。
1)増える、介護をする人、仕事をしながら介護を担っている人、介護のために無業となる人:「令和4年就業構造基本調査」から
・統計局ホームページ/令和4年就業構造基本調査の結果 (stat.go.jp) から引用転載しました。
15 歳以上人口で、就業状態及び介護の有無別にみると、介護をしている者は629万人、うち有業者は365万人。(表7-2、図7-2)
過去10年間の推移では、介護をしている者は、2012年から2017年にかけては70万人の増加、2017年から2022年にかけては1万人の増加。
このうち有業者については、2012年から2017年にかけては55万人の増加、2017年から2022年にかけては18万人の増加。(図7-2)
介護をしている者に占める有業者の割合は、58.0%で5年前に比べ2.8ポイントの上昇。
男女別にみると、男性が67.0%で5年前に比べ1.7ポイントの上昇、女性が52.7%で3.4ポイントの上昇。(表7-2)
年齢階級別に40歳以上についてみると、男性は「50~54歳」が88.5%で最も高く、5年前に比べ1.5ポイントの上昇で、女性は「50~54歳」が71.8%で最も高く、5年前に比べ4.4ポイントの上昇。(表7-2)
有業者と無業者の数の推移
有業者は、介護を行いながら仕事を続けている人の数を示しており、介護と仕事の両立を図っている人々の状況を理解できます。
無業者は、介護のために仕事を辞めた人、もしくはもともと仕事に就かずに介護を担っている人の数です。ここから、その一部は、介護離職を経験した人々であるわけです。
有業者と無業者の数の推移を示すデータをグラフから読むと、2015年から2023年にかけて、有業者は増加し続け、無業者の数も増加していることが分かります。


前職を介護・看護のために離職した者の数の推移
前職を介護・看護のために離職した者の数は年々増加しており、以下のデータが示されています。


ただし、この調査では、介護と看護双方を合わせてのデータであるため、参考にとどめたいと思います。
2)介護離職までの期間が短い事情:「仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業(令和3年度厚生労働省委託事業)」から
次に以下の資料からです。
⇒ 「仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業(令和3年度厚生労働省委託事業)」
介護離職までの期間
前職を介護・看護のために離職した者の数は年々増加しています。
この調査結果で、離職者について、手助・介護を始めてから、手助・介護のために仕事を辞めた時までの期間をみると、半年未満が過半約55%超を占めており、介護を初めて短い期間で離職している人の多いことがうかがえます。
この結果から、あくまでも推測ですが、急に仕事を辞めることに、やめざるを得ないことになってしまったのではと感じさせられたのです。
こんなはずじゃなかった、まさか辞めなきゃどうにもしようがなかった・・・。
そのことから、介護とはなにか、介護することになるとどうなるか、なにをしなければいけないのかを含め、介護の知識や介護への備えがなかった、あるいは少なかったのでは。
この視点が、このシリーズを構想し、始める動機・きっかけの一つになっているのです。

3)深刻化する家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者数の推移と予測:「経済産業省 介護政策」から
もう一つ、この資料を加えました。 ⇒ 介護政策 (METI/経済産業省)
家族介護者、ビジネスケアラー、介護離職者の推移
まず先に、別資料ですが「令和3年度介護保険事業状況報告」によれば、2021年(令和3年)の要介護認定者数が689.6万人。
昨年は、約700万人であり、今年団塊世代の全員が後期高齢者となる今年2024年以降は、その数も急速に増加することは間違いありません。

一方、先述した経産省資料によると、介護に関する3種類の人数の推移と予測が、次のようになっています。
※下記画像参照
家族介護者:
・2015年: 約593万人 ・2020年: 約678万人 ・2023年: 約795万人(予測)
ビジネスケアラー:
・2015年: 約232万人 ・2020年: 約262万人 ・2023年: 約307万人
介護離職者:
・2015年: 約9万人 ・2020年: 約7万人 ・2023年: 約11万人(予測)

以上のデータから、今後介護と向き合う必要がある人が右肩上がりに増え、ますます介護離職の問題が深刻化することが予想されます。
3. 介護離職経験者事例紹介
こうした状況と今後の予測を確認しながら、実際に介護離職を経験した方の事例を2つ紹介しておきたいと思います。
事例1: 50代男性Aさんのケース(正規社員)
状況: Aさんは大手製造業で働く正社員で、技術職を担当していました。仕事のストレスと長時間労働が続く中、母親が認知症を発症し、介護が必要になりました。
Aさんの妻は病気で早くに亡くなっており、大学生の息子は家を出て生活しているため、Aさんが母親の介護を主に担うことになりました。
離職の経緯: 初めは介護サービスを利用しながら仕事を続けていましたが、母親の状態が悪化し、要介護度が高くなり24時間介護が必要になったため、仕事を辞めざるを得なくなりました。
離職後の状況: 離職後、Aさんは収入がなくなり、生活費の捻出に苦労しました。また、在宅介護でのやり方も、デイサービスや場合によっては宿泊付き介護の活用などで対応できる見通しが付きかけたことから、パートでの再就職を試みましたが、定時勤務が難しいことが多いことから、適切な仕事がなかなか見つからない状況が続きました。息子はアルバイトを増やし、自身の学費や生活費の補填に充てています。
対応と教訓: Aさんは、介護に関する知識を深めるために介護資格の取得をめざし、現在は介護施設で働きながら、母親の介護を続けています。彼は、介護と仕事を両立させるための計画と準備の必要性・重要性を強調しています。また、在宅介護が困難な場合に備えて、施設介護の選択肢も検討しています。
事例2: 40代女性Bさんのケース(非正規社員)
状況: Bさんは中小企業で働く非正規社員で、事務職を担当していました。母親が脳卒中で倒れ、半身不随になり、介護が必要になりました。Bさんはシングルマザーで、小学生の娘と一緒に暮らしています。
離職の経緯: 初めはデイサービスを利用しながら働いていましたが、母親の状態が悪化し、自宅での介護が必要になりました。Bさんは収入の減少と介護負担の増加に直面し、最終的に離職を決断しました。
離職後の状況: 離職後、Bさんは自身の少ない貯蓄と母親の年金を生活費と介護費に充てて、介護に専念しています。しかし、当然生活費の捻出に苦労し、娘の教育費も不安を抱えたままです。収入の不安定さから、Bさんは経済的に非常に厳しい状況に立たされており、生活保護の受給を申請する必要があることも最近考えています。
対応と教訓: Bさんは、地域の支援制度やNPOのサポートを積極的に利用しています。また、在宅介護と施設介護のバランスを考え、母親の状態に応じた介護方法をケアマネジャーに意見を聞くなどして工夫しようとしています。彼女は、介護離職を防ぐために、事前に介護の知識や支援制度について学んでおくことの重要性を感じています。また、可能であれば親族や友人の助けを借りることも検討しています。
このように介護離職で苦労した方が、全国各地に大勢いらっしゃると思います。
しかし、介護離職の背景や実際の苦労は、やむなく離職をした人・ケースの数と同じ数のパターンがあり、すべてが異なるわけです。
そうした介護離職に至らないように、ほとんどの方々に明日、あるいは近い将来、あるいはある日突然起こりうる家族介護への備えを日々の生活を通じて行っていくうえで参考になる内容を、当シリーズで提案・解説していきたいと思っています。
以上、介護離職の意味や介護離職についての現状・今後の予測などを、関連した事項と数値を公的な調査や資料を参考にして見てきました。
次回は、「第1章 介護離職とは?その現状と原因」の第2項<介護離職の主な原因と影響>をテーマとします。
なお、以下のシリーズの全体構成を見て頂ければ、介護離職をしないためには、これからどのように準備していけばよいかを分かって頂けるかと思います。
どうぞ宜しくお願いします。

介護離職しないための8ステップ+1と実践法
1. 介護離職とは?その現状と原因
2. 介護保険制度、保険外制度の活用と介護離職防止
3. 介護施設・在宅介護の選択肢と介護離職防止
4. 自治体と地域の支援制度を理解し活用する
5. 仕事と介護の両立を支援する制度を理解し活用する
6. 企業による介護離職防止策の取り組みと活用
7. 家族との介護協力と介護離職防止対策
8. 介護離職防止を想定しての介護の事前準備・計画と相談
9. 万一の介護離職後の再就職・転職とキャリア構築