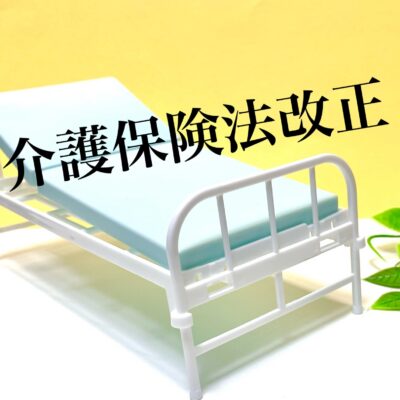【今日からできる】介護保険の基本から身体介護まで、家族介護者が知るべき全知識
「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズを、最後に添付している構成に従って進めてきています。
今回は、「第8章 介護離職防止を想定しての介護の事前準備・計画と相談」の最終回です。
本記事に、広告を挿入することがあります。
「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズー30
第8章 介護離職防止を想定しての介護の事前準備・計画と相談
8-3 家族介護の基礎知識と日常の介護・介助の実践法
はじめに
家族の介護を担う際には、日常生活の中で必要な介護や介助を適切に行うための知識と技術が求められます。
本記事では、介護保険制度の理解から、日常的な介護・介助の具体的な方法、さらには介護者自身のケアに至るまで、家族介護に円滑に取り組むために知っておくべきポイントを網羅的に解説します。
これにより、家族の介護に取り組む方々が、安心して介護を続けられるようサポートします。
1.介護生活のための基礎知識
1)介護保険制度の概要の理解
介護保険制度は、要介護者が必要な介護サービスを受けるために設けられた仕組みです。
この制度の基本的な仕組みを理解することは、適切なサービスを選び、効率的に介護を進めるために不可欠です。
・介護保険の基本的な仕組み
介護保険は、全国の40歳以上の人が加入し、保険料を負担することで成り立っています。
要介護認定を受けた方は、この保険を利用して在宅介護サービスや施設介護サービスを受けることができます。
介護サービスの利用には、ケアマネージャーとの相談が必要で、個々の状況に応じたケアプランが作成されます。
介護保険制度の基本的な仕組みを理解することは、適切なサービスを利用するための第一歩です。
介護保険の適用範囲や、利用できるサービスの種類についての基本的な知識を持っておくことが重要です。
・サービスの選び方
介護保険を利用する際には、被介護者の状態や家庭の状況に応じて、最適なサービスを選択することが求められます。ケアマネージャーと相談しながら、必要なサービスを的確に選ぶ方法を学びましょう。
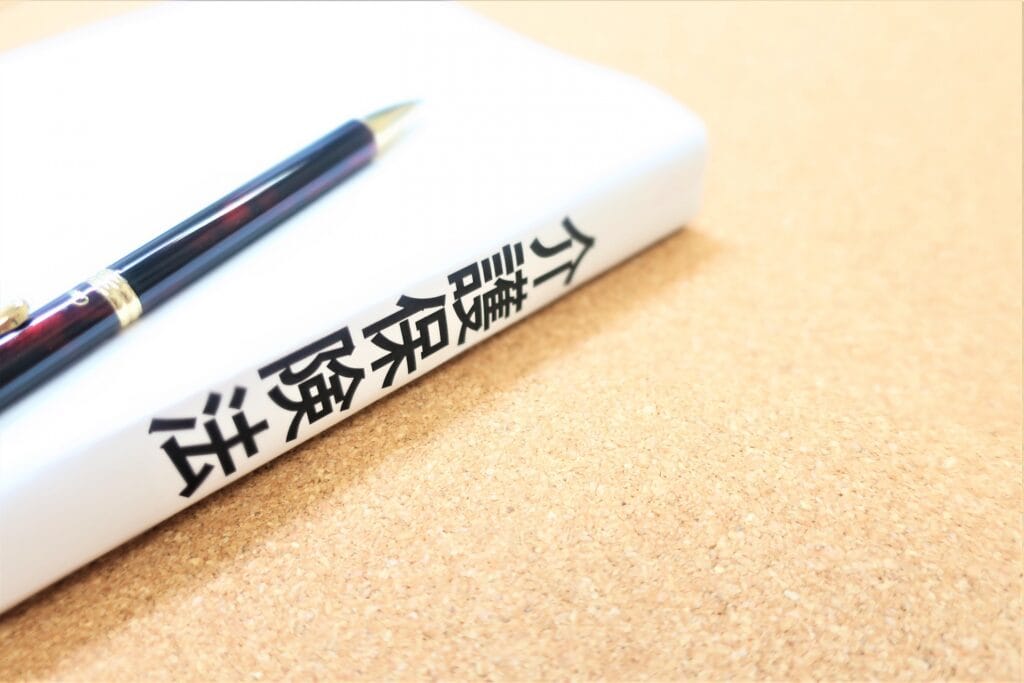
2)要介護者への生活援助
訪問介護における生活援助とは、日常生活を支援するためのサービスを指します。
具体的には、買い物代行、掃除、洗濯、料理など、被介護者の日常生活をサポートする行為が含まれます。
(参考):「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
<具体的な生活援助内容>
・掃除:居室内やトイレ、卓上等の清掃/ゴミ出し/準備・後片づけなど、被介護者が生活する空間を清潔に保つための掃除を行います。
・洗濯:洗濯機または手洗いによる洗濯/洗濯物の乾燥(物干し)/洗濯物の取り入れと収納/アイロンがけ
・ベッドメイク:利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
・衣類の整理・被服の補修:衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)/被服の補修(ボタン付け、破れの補修
等)
・一般的な調理、配下膳:配膳、後片づけのみ/一般的な調理等、被介護者の食事を準備し、栄養バランスの取れた食事を提供し、後片付けも行います。
・買い物・薬の受け取り(代行):日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)/薬の受け取り等食材や日用品の買い出しを代行し、必要な物品を被介護者に届けます。
訪問介護で契約に基づいて行う生活援助ですが、家族は普通にこうした援助を、要介護者である親や兄弟姉妹などに日常的に行っています。
特に難しい技能・技術が必要なわけではないですが、要介護の家族に毎日当たり前のように継続するのは、やはり大変なことです。
訪問介護という外部サービスには費用負担責任が発生しますが、家族が行う場合には支払われることがないのが普通です。

3)要介護者への身体介護
身体介護は、要介護者が日常生活を送る上で必要な身体的サポートを行う行為です。
これには、入浴、排泄、食事、着替えの介助などが含まれます。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」に記載されている具体的な区分を理解し、適切な介助を行いましょう。
(参考):「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」
<具体的な身体介護・介助内容>
・入浴介助:安全に入浴できるようサポートし、転倒などのリスクを軽減します。
・排泄介助(トイレ利用・ポータブルトイレ利用・おむつ交換):トイレへの移動や便器への座り方をサポートし、排泄がスムーズに行えるよう手助けします。
・食事介助:自分自身で食事を取ることが困難な場合や手助けが必要なおりの介助です。特段の専門的配慮をもって行う調理も含みます。
・清拭・入浴、身体整容:清拭(全身清拭)/部分浴(手浴及び足浴・洗髪)/全身浴/洗面等/身体整容(日常的な行為としての身体整容)/更衣介助など、入浴に伴う介助作業です。
・体位変換、移動・移乗介助、外出介助:身体的な移動や活動の際に介助や手助けを行います。
・起床及び就寝介助:起床・就寝時の介助です。
・服薬介助:間違って薬を服用しないよう、あるいは服用を円滑にできるよう介助します。
・自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等:やや専門的な表現になっていますが、見守り的な援助です。
上記の一部について、次の項で再度取り上げています。

4)要介護者とのコミュニケーション、メンタルケア
介護においては、身体的なケアだけでなく、心のケアも非常に重要です。要介護者とのコミュニケーションを円滑に行い、安心感を与えることが、メンタルケアの基盤となります。
<コミュニケーションの重要性>
・心のケア:介護は身体的なケアだけでなく、精神的なサポートも重要です。
被介護者の感情や気持ちに寄り添い、安心感を与えることが大切です。コミュニケーションを通じて信頼関係を築くことが、質の高い介護を提供するための基盤となります。
・共感と傾聴:要介護者の話をしっかりと聞き、共感することで信頼関係を築きます。
・心理的サポート:感情や不安に寄り添い、日常生活の中で安心感を提供します。
2.主な身体介護・介助方法の理解と習得
ここでは、身体介護・介助の主なものを確認します。
普段の介護で行っていることが多いかもしれませんが、時折り介護に協力することになった場合や、初めて介護をおこなうようになる時に備えて、理解し、必要時に実践できるように、と思います。
1)食事介助の方法
食事介助は、被介護者が安全に食事を取れるようサポートする重要な介助です。誤嚥を防ぎ、栄養を確保するための適切な方法を習得しましょう。
<食事介助の基本>
・食事の準備: 食べやすい大きさや形状に食材を整え、飲み込みやすい状態にします。
・安全な食事提供、嚥下(えんげ)のサポート:食事介助においては、窒息を防ぐための注意が必要です。
例えば、食べ物の形状や大きさに配慮し、被介護者が安全に食事を取れるようサポートします。
また、飲み込みに問題がある場合には、嚥下のサポート技術も学んでおくことが大切です。
・食事環境の整備、姿勢の調整:食事をより快適に、楽な姿勢で取れるように、食卓の位置や椅子の高さなどを調整し、リラックスした環境を整えることも重要です。これにより、被介護者が食事を楽しむことができ、栄養状態の改善にもつながります。
2)移動・移乗介助の方法
移動や移乗の介助は、被介護者が安全に移動できるようサポートする技術です。正しい姿勢や動作を習得することで、介護者の負担も軽減されます。
<移動・移乗の基本>
・正しい姿勢と動作:移動や移乗の際には、介護者自身の体を守るために正しい姿勢と動作を心がけることが大切です。例えば、腰を痛めないように膝を使って持ち上げる動作や、重心を低く保つ方法などを実践したいと思います。
・安全な移動: 被介護者の身体に配慮しながら、適切に体を支えます。
・補助具の使用: 車いすや歩行補助具など、適切な補助具を活用することで、移動のサポートがより安全かつ効果的に行えます。これらの補助具の使い方を知っておくことで、介護者と被介護者双方の負担軽減につながります。

3)排泄介助の方法
排泄介助は、被介護者が快適に排泄できるようサポートする技術です。プライバシーに配慮しつつ、適切な支援を行いましょう。
<排泄介助の基本>
・プライバシーの尊重:排泄介助を行う際には、被介護者のプライバシーを尊重することが重要です。ドアを閉めたり、体を覆うなどの配慮を怠らないようにしましょう。
・安全な移動とサポート:トイレへの移動や便座への移乗の際には、被介護者が自立して動くことができる範囲で安全にサポートします。適切なサポートにより、転倒や怪我のリスクを減らすことができます。
4)入浴介助の方法
入浴介助は、被介護者が清潔を保ち、リラックスできる時間を提供するための介助です。安全性を確保しつつ、快適な入浴をサポートします。
<入浴介助の基本>
・安全確認: 入浴前に浴室の温度や水温を確認し、滑り止めなどの安全対策を講じます。
・身体の支え: 入浴中は、転倒や事故を防ぐためにしっかりと身体を支えます。
5)外来診療付き添い
外来診療に付き添う際には、病院までの移動や診察中のサポートを行います。被介護者が安心して診療を受けられるよう、適切なサポートを提供します。
<外来診療の付き添い基本>
・移動サポート: 病院までの移動をサポートし、スムーズに診療を受けられるようにします。
・診療中のサポート: 診察中や待機中のメンタルケアを行い、安心感を提供します。
主な身体介護・介助方法を理解し、実践することで、被介護者の生活の質を向上させることができます。
適切な介助技術を身につけ、日常のケアを少しでも円滑に行えるよう努めていくことができればと思います。
3.介護者の心身のケアの重要性
1)介護者自身のケア
介護者自身が健康であることが、長期にわたる介護を支えるために不可欠です。心身の健康を維持するためのケアを行いましょう。
<自己ケアの基本>
・休息の確保:十分な睡眠と休息を取り、心身の疲労を軽減します。
・ストレス管理:ストレスを抱え込まず、折に触れて解消できるよう、メンタルヘルスを保ちます。
2)介護協力家族のケア
介護に協力する家族のケアもまた重要です。家族全員が健康を維持し、支え合うことで、介護を円滑に進めることができるようにしたいものです。
<家族ケアの基本>
・コミュニケーションの維持:家族間でのコミュニケーションを大切にし、お互いの状況を理解し、補完しあうことができればと思います。
・役割分担・介護の負担が偏らないように適度に分担し、家族間での役割分担を調整できればと思います。
介護者とその家族が健康を維持することは、長期的な介護を支えるために非常に重要です。自己ケアと家族ケアを怠らず、協力し合いながら介護を続けることができればと思います。

まとめ
本記事では、家族介護の基礎知識と日常の介護・介助の実践法について、包括的に整理してみました。
適切な介護方法を理解し、日々のケアに取り入れることで、被介護者の生活の質を向上させるとともに、介護者自身の健康も守るように努めましょう。
家族の皆さんが協力し、安心して介護に取り組める環境を整え、維持していくことができるようにと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本稿は、一旦閉鎖した当サイトで2024年9月11日に公開した記事を、サイト再開に伴い、本日再掲したものです。
当時の実態と現状では異なる内容が含まれていることがあり得ます。ご了承ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー