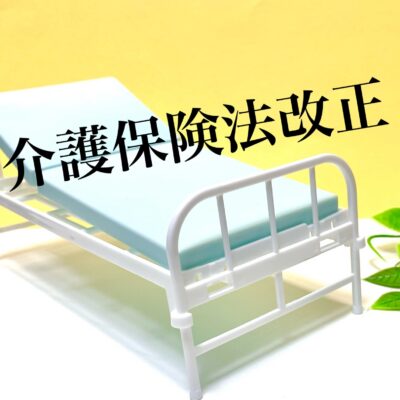介護離職を防ぐ!最適な介護場所・方法の選び方と実践ガイド
本稿は、一旦閉鎖した当サイトで2024年8月11日に公開した記事を、サイト再開に伴い、本日再掲したものです。
当時の実態と現状では異なる内容が含まれていることがあり得ます。ご了承ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズ。
今回は、「第3章 介護施設・在宅介護の選択肢と介護離職防止」の第5回最終回「介護の場所の選択・方法の選択と介護離職防止対策」で、総括を兼ねています。
本記事に、広告を挿入することがあります。
「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズー13
第3章 介護施設・在宅介護の選択肢と介護離職防止
3-5 介護の場所の選択・方法の選択と介護離職防止対策
今回は、この章のこれまでの全4回の記事の総括に当たるものとして位置付けています。
確認を繰り返しながら総括し、次章へ繋げることも目的としています。
1.介護形態を決定する介護資源と条件を確認するー チェックリスト活用法
介護の場所や方法を選択する際には、以下のような介護資源と条件を確認することが重要です。
チェックリストを活用して、適切な介護形態を選びましょう。
<介護資源の確認>
・家族のサポート体制
家族全員が介護に対する意識を共有し、どれだけ協力できるかを確認することが必要です。例えば、介護に対する意欲や協力体制がどの程度整っているかを評価します。
・経済的資源
介護には多くの費用がかかるため、資金計画を立てることが重要です。具体的には、介護保険や助成金などの公的支援制度の活用を考慮し、自己負担額を把握しておきましょう。
・地域の介護サービス
地域で提供されているデイサービスや訪問介護などのサービスを確認し、それらをどのように活用できるかを検討します。これにより、家族の負担を軽減し、適切なサポートを受けることが可能になります。
<条件の確認>
・被介護者の状態
被介護者の健康状態や要介護度を評価し、どの程度の介護が必要かを把握します。また、精神的な安定性や認知症の有無も確認することで、最適な介護方法を選ぶ材料とします。
・住環境
自宅のバリアフリー化や介護設備の整備状況を確認し、必要に応じて改善することが求められます。例えば、手すりの設置や介護ベッドの導入などが挙げられます。
・介護者の負担
介護者自身の健康状態や精神的な負担を考慮することも重要です。介護者が無理をせず、長期にわたりケアを続けられるような環境づくりが必要です。
<チェックリストの活用法>
・優先順位の設定
介護において重要な項目を明確にし、優先順位を設定することで、必要なチェックリストを作成します。これにより、どの介護形態が最適かを選びやすくなります。
・選択肢の評価
チェックリストを活用して、各選択肢のメリット・デメリットを評価します。その結果、家族や被介護者にとって最適な介護形態を選ぶことが可能になります。
-------------------------------
上記の要素も反映させて、介護形態を決める上で正しく現状を把握し、望ましい結論に導く上での確認すべき課題/項目を整理し、チェックリストを作ってみました。
但し、チェックがかかった項目数や区分ごとのバランスなどによって、自動的にどういう介護形態が望ましいか、必要かという結論・結果がでるわけではありません。
これらの項目の内容を整理することが、望ましい介護の方法を決定する上での参考になる、あるいはできると理解しておくとよいでしょう。
【介護形態を決定するためのチェックリスト】
1. 被介護者の状態
□ 健康状態(病歴、現在の病状)
□ 介護の必要度(要介護認定のレベル)
□ 精神状態(認知症の有無、精神的な安定性)
2. 家族のサポート体制
□ 家族の介護に対する意識(意欲と協力体制)
□ 家族の健康状態(介護者の身体的・精神的健康)
□ 家族のスケジュール(仕事や他の家庭責任との両立)
3. 経済的資源
□ 介護にかかる費用の予算(短期・長期)
□ 公的支援制度の利用状況(介護保険、助成金)
□ 自己負担可能額(毎月の介護費用として支払える金額)
4. 住環境の整備
□ 自宅のバリアフリー化(手すり、スロープの設置)
□ 介護設備の整備状況(介護ベッド、車いす)
□ 介護スペースの確保(介護に適した部屋の有無)
5. 地域の介護サービス
□ 利用可能な訪問介護サービス(内容と費用)
□ 利用可能な訪問看護サービス(内容と費用)
□ デイサービスの有無と内容(リハビリ、レクリエーション)
□ ショートステイの有無と内容(短期入所、休養目的)
6. その他の考慮点
□ 介護者の負担軽減策(レスパイトケアの利用)
□ 緊急時の対応計画(緊急連絡先、緊急時の対応策)
□ 介護者と被介護者の相性(相互理解とコミュニケーション)
--------------------------------
2.介護する人、介護される人の相互理解と介護制度・介護サービス生活の理解
介護する人と介護される人の相互理解を深めることが、スムーズな介護生活の鍵です。
また、介護制度や介護サービスを理解し、効果的に活用することも重要です。
<相互理解の促進>
・コミュニケーションの確立
定期的に話し合い、介護する側とされる側の気持ちやニーズを共有することが重要です。
例えば、被介護者の不安や不満を聞き取り、介護者のストレスや負担についても理解を深めることで、お互いの信頼関係を築きます。
・感情の理解
介護される人の不安や不満、介護する人のストレスや負担に対して共感し、理解することが大切です。
このような感情の理解が、円滑な介護生活を支える基盤となります。
<介護制度の理解>
・介護保険制度
介護保険制度の仕組みや利用方法を理解することで、適切なサービスを選びやすくなります。
これにより、被介護者に適切ななケアを提供するための支援を受けることができます。
・公的支援制度
自治体や国が提供する支援制度を活用し、経済的な負担を軽減することも重要です。
例えば、助成金や公的介護保険を適切に利用することで、家庭の負担を減らすことが可能です。
<介護サービスの理解>
・訪問介護・訪問看護
在宅で提供されるサービスの内容と利用方法を理解し、被介護者の生活の質を向上させることが重要です。
適切なサービスを選ぶことで、被介護者にとって最適なケアを提供できます。
・デイサービス・ショートステイ
外部施設で提供されるサービスの利用方法を学び、被介護者と家族のニーズに合ったサービスを選ぶことが求められます。
これにより、家族の負担を軽減し、介護離職を防ぐためのサポートを得ることができます。
この中でも触れましたが、一般的に「コミュニケーション」という言葉で簡単に片づけてしまいがちですが、実際には、そう簡単にコミュニケーションを持ち、しっかり意思疎通すること、同意を形成することは難しいのが現実です。
介護する人、介護される人とシンプルな関係にとどまらず、他に家族がいる場合、複雑かつ困難になる可能性が増します。
現在住んでいる場所が違うこともありますし、もちろん性格や仕事・預貯金等資産その他、種々の利害関係も絡み合って、教科書のようにコミュニケーションを通して良い人間関係を作ることは、むしろ難しいのではと思います。
前項で提案した<チェックリスト>の構成項目を見ただけでも、そのすべてについてコミュニケーション課題とし、必要な決定や確認を行うことが簡単ではないことが分かると思います。
その改善解決について詳述する必要があると思いますが、機会を改めて行いたいと思います。
チェックリストの各項目の意味するもの、内容などを見える化する必要もありますし。
3.介護離職防止に役立つ在宅介護と施設介護の組み合わせとその他の要素
介護離職を防ぐためには、在宅介護と施設介護を組み合わせることが有効です。
また、その他の要素も考慮する必要があります。
一応、以下の記事を参考にして頂ければと思いますが、要点のみ、確認の意味でメモしておきます。
⇒ 自宅介護と施設介護の併用方法と費用比較:結城康博氏の視点から見る使い方と負担軽減策 (kaigoshukatsu.com)
<在宅介護と施設介護の組み合わせ>
・併用の利点
在宅介護と施設介護を組み合わせることで、家族の負担を軽減し、被介護者に最適なケアを提供できます。
例えば、週に数回のデイサービス利用や、定期的なショートステイの活用が効果的です。
・併用事例
週に数回デイサービスを利用し、必要に応じてショートステイを組み合わせることで、家族と被介護者双方の負担を分散させることができます。
このような併用事例を参考に、自宅介護と施設介護のバランスを取ることが重要です。
<その他の要素>
・フレキシブルな介護計画
介護の状況は常に変わる可能性があるため、状況に応じて柔軟に介護計画を変更することが大切です。定期的に見直しを行い、最適な介護計画を維持しましょう。
・職場との連携
介護離職を防ぐためには、職場の理解とサポートを得ることが必要です。
上司や同僚とのコミュニケーションを通じて、介護と仕事を両立させるための協力を求めることが大切です。
・地域資源の活用
地域の支援サービスやボランティア活動を活用し、家族の負担を減らすことも重要です。
地域に根ざした支援ネットワークを活用することで、介護生活の質を向上させることができます。
4.結城康博氏著『在宅介護』「最終章これからの在宅介護はどうあるべきか」による提言
最後に、先の記事でも取り上げましたが、ほぼ10年前に発刊された結城康博氏の『在宅介護』の「最終章 これからの在宅介護はどうあるべきか」から、今後の在宅介護のあり方についての提言を総括の一部として紹介します。
<在宅介護の未来>
・共生社会の実現
高齢者と若者が共に支え合う社会の構築を目指すことが、これからの在宅介護の重要な課題です。
世代を超えた共生社会の実現が、高齢者の生活の質を向上させます。
・地域包括ケアシステム
地域で完結するケアシステムの整備が、今後の在宅介護においてますます重要となるでしょう。
地域全体で支えるケア体制を構築することで、持続可能な介護を実現します。
<家族介護の支援>
・家族の負担軽減
家族介護者の負担を軽減するための具体的な支援策が求められます。
例えば、レスパイトケアや訪問介護の充実が、家族の負担を軽減する鍵となります。
・介護者の育成
介護者の教育・研修を充実させ、質の高い介護を提供できる人材を育成することが重要です。
介護者のスキル向上が、被介護者の生活の質を向上させます。
<社会全体での取り組み>
・介護の社会化
介護を家族だけでなく、社会全体で支える体制を整備することが求められます。
介護の社会化が進むことで、家族の負担を大幅に軽減することが可能です。
・持続可能な介護制度
持続可能な介護制度を構築し、将来の高齢化社会に対応できるようにすることが重要です。
制度の改善と適切な財源確保が、長期的な介護の安定を支える鍵となります。
結城氏の提言は、介護を社会化するという、社会福祉専門家が好んで用いる「社会化」をキーワードの一つにしているのが特徴です。
専門家の言としては当然のことですが、私自身は、この結論に無条件で賛成はしていません。
なぜなら「社会化」の「社会」は均一の条件であることを意味しませんし、必ずばらつきが生じます。
そして関連する法律・法規そのものも自治体により違いがありますし、社会の枠組みを、ボランティアやNPOに広げると、やはり違いがあります。
そして何よりこの場合意味する「社会」の中心・軸である国、国政が政党により、政権によりブレが生じるからです。
企業がこの社会に加えられると、一層その格差・違いが拡大します。
結城氏に期待し、評価するのは、介護制度自体の在り方への指摘・提言であることをここで確認しておきたいと思います。
本書は介護に関する書のバイブルと評価しています。ほぼ10年前に出版され、問題提起している書ですが、本質的な問題は現在も何ら変わることがありません。ご一読をお薦めします。
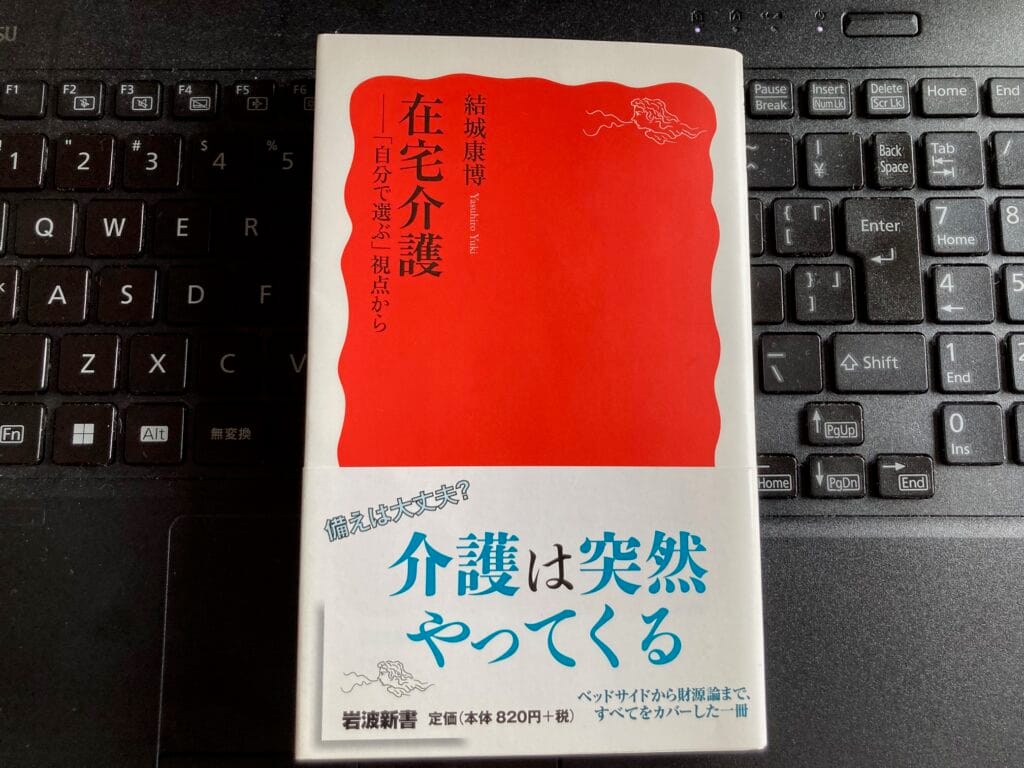
5.介護離職防止のための介護選択、究極のポイント:第3章総括
介護離職はなんとしてでも防ぐべき。
これを何とか現実のものとできるように、これからの介護に備えて頂きたい。
そういう目的・意図でこのシリーズ「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」に取り組んでいます。
この第3章では、
・自宅と介護施設で
・どのような介護作業・介護サービスを行うか、どのような介護生活を送ることになるのか
・自宅・施設、作業・サービスなどの活用法なども踏まえてイメージし、
・自らその介護生活と介護サービスにどう関わることができるか
等を考えて頂けるよう、繰り返し説明してきました。
その基本的な理解とイメージ化こそが、介護離職は何としてもせずに、望ましい介護生活を実現することに繋がると考えています。
そのための究極的なポイントは、
・絶対に介護離職はしない、せずに望ましい介護を実現し、望ましい介護生活を送る、という強固な意志を持つこと、
・そのための準備・備えを、これからの日常生活を通して着実に実践する、と決意すること
にあります。
ここまで、「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」の3つのステップを踏んできました。
次回からは、第4ステップ「自治体と地域の支援制度を理解し活用する」に入ります。

※ 前の記事はこちらで:
※ 次に記事はこちらへ: