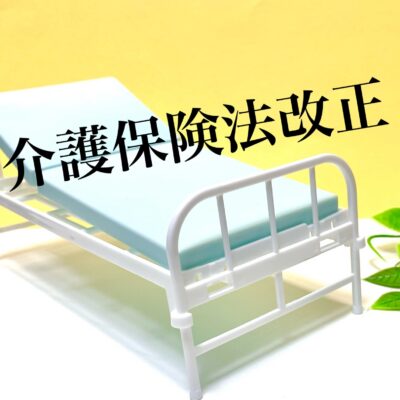100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月)
5.永代供養墓の契約は私たち夫婦の終活を兼ねて(2022/9/19)
100歳の義母を特養で看取り、特養退去、亡骸の葬儀場への移送、納棺、通夜、そして火葬・骨上げ。一連の見送りまでの回想をここまでに行ってきました。
今回は、見送りに関係するもう一つの課題、お墓をどうするか、どうしたかについての回想です。
看取りから見送りまで一連の終活体験後、準備が整えば遺骨を埋葬するお墓とその契約に至った経緯と寺院の話です。

タイミングよく?永代供養墓苑見学会の新聞折込チラシ
8月24日に、義母がお世話になった特養の施設長に御礼のご挨拶に行った日の前後に、永代供養墓の見学会開催
の新聞折り込みチラシが。
妻が、「お骨をいつまでも家に置いておくのは」と不安を抱いていた折り。家からも比較的近い寺院だったので、26日(金)に行ってみることに。
ついでに、ネット検索で岡崎市内で永代供養の樹木葬の募集をしている寺院があったので、資料請求を。
どちらも、宗旨、宗派は問わず、永代供養が謳い文句。
見学に行った寺院の永代供養墓は次の2種類
・絆墓苑:永代供養料(2人まで)35万円、墓石33万円、計68万円(税込)
・同SP:永代供養料(2人まで)55万円、墓石44万円、計99万円(同)
前者は、箱状の墓石に名前を刻むもの。
後者は、碑銘版と収骨スペースであるカロートがある一応お墓の形状のもの。
まず、妻の実母、私の義母のお墓なので、別姓で名前を入れる必要があります。
SPの方は、1人に付き永代供養料20万円、墓石業者への手数料5万円と墓石への名彫り料2万円の追加料金を払えば5人まで祀ってもらえる。
申込者は私の〇〇姓なので「〇〇家」と墓石に表示しますが、別姓者も併記してもよいわけです。
私としては、当然私たち夫婦も同じ墓に入るわけで、どちらが後先になってもよいよう、追加料金を払って3人分契約をしておくのがよいのでは、と。
妻は、当初考えていたよりも多額の出費になるので、少しばかり躊躇し、即断は避けたい意向。
一応、現地の場所・環境を確認し、現物を見学し、条件等の説明を受けて、仮申込みということで希望の位置のお墓を押さえておいてもらうよう依頼。
しかし、車中話し合いをし、移動中に利用申し込みの電話を。
翌々日28日(日)に再度寺院に出向き、営業担当者に、正式に1人追加の3人での申込み。
住職との面会・契約の日を9月1日に決定。
住職との面会・契約、「霊園永代使用権証書(墓地使用許可証)」受領、永代供養料3人75万円
当日支払ったのは、永代供養料(3人分)75万円。
墓石料等、営業会社への支払い分51万円は、1週間以内に指定銀行振り込み。
永代供養費の支払いを済ませた後、「墓地使用許可証」に当たる「霊園永代使用権証書」を受け取り、その後、種々の質疑応答を。
まず、妻が最も気にしている、今後の供養などの付き合い方・対応の仕方。
寺院での年間の定例供養は、次の通り。
・新年1月第1土曜・日曜の正月の供養
・3月の春のお彼岸の供養
・7月のお盆の合同供養
・9月の秋のお彼岸の供養
の4回で、都度案内を郵送可能。
郵送が不要ならば、その旨申し出ればよく、参加義務はないとのこと。
妻は、来年の初盆の供養をもう気にかけており、この7月のお盆の合同供養の案内だけ頂き、その参加後のご案内は無用とお願いすることに。
また一般的に納骨は49日明け後にということに倣い、追って納骨と供養をお願いする日を連絡することに。
但し、その日をお墓開きと納骨式を同時に行うことが可能であることを確認。

最も気になった「カロート」へ納骨方法。麻袋か骨壷か
実は、もっとも聞きたかったのが、カロートと呼ばれるお骨を納める場所への実際の納骨・収骨方法です。
当然、骨壷で納めると思っていたのですが、その場で聞くと、持参した骨壷から麻袋に骨を移し、その袋を納めるとのこと。
知らなかったとはいえ、びっくりでした。
いずれ土に還る、ということ。
また骨壷には水が入り、非常に悪い状態になるから、ということでもありました。
その場では、ああそうですか、と怪訝に思いながらもおさめて来たのですが、帰宅してからも気になり、ネットで調べてみると、骨壷で収めている例も当然ありました。
私たちとしては骨壷で収めたいねとして、営業の墓石社の担当に連絡すると、住職と直接話をして欲しいと。
ご住職に連絡すると、骨壷でも構わないと了解を得たのですが、骨壷に水が溜まるのは、器の中が露結するからだとの説明を受けました。
雨水などが壺に入ってくるのかとイメージしていましたが、露が付くから。
なるほど・・・。
そこで今考えているのは、骨壷と麻袋、両方を収めて、変化具合を調べる。そして、私か妻かどちらかを次に入れる場合、どちらがよいか試しておいて決めようか、というプランです。
不謹慎ではありますが。
いずれにしても、こうした納骨、供養、祭祀等は地方によって違いがあるとのこと。
無宗教の私としては、誰にも迷惑をかけずに、自由にやれればと思っているのですが、なかなかそうもいかないようです。
「永代供養墓使用規則」から
参考までに、一部、納得できない事項もあるのですが、手渡された「永代供養墓使用規則」の重要部分を確認すべく、以下に転記しました。
第一条(趣旨)
〇〇寺(以下、当寺院)は、永代供養〇〇寺(以下〇〇寺)の趣旨に賛同し、かつ所定の手続きを完了した人の使用に供するものとする。
第二条(使用の承諾と使用者)
〇〇寺を使用する者は、この規則に定めるところにより当寺院の許可を受けなければならない。
使用者は、墓地継承者及び縁故者がいない者に限る。
また使用者は自らが属する宗教宣伝活動を墓地内及び〇〇寺領内において行わない。
第三条(管理)
〇〇寺の管理は、当寺院が行う。
第四条(使用手続き)
〇〇寺に埋葬する者は、当寺院所定の申込書及び契約書に、必要事項を記入の上、永代供養料を添えて永代供養許可を申請しなければならない。
但し、納金された永代供養料は理由の如何にかかわらず、一切返還しないものとする。
第五条(墓地使用許可証の交付)
1)当寺院が前条の申請を受理した時は、所定の手続きを完了した後、墓地使用許可証を交付する。
2)墓地使用許可証の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当寺院に訂正の届け出をしなければならない。
第六条(埋葬方法)
〇〇寺に33回忌まで埋葬し、33回忌を過ぎた後は永代供養塔に合葬し、当寺院が永代に供養管理する。
なお33回忌とは最後の埋葬者から33回忌までとする。
第七条(埋葬権譲渡の禁止)
〇〇寺の埋葬は、記名された埋葬者(予定者)限りとし、申請者は埋葬権を第三者に譲渡または転貸ししてはならない。
第八条(埋葬後の祭祀権利)
〇〇寺への埋葬された後の遺骨の祭祀権は当時寺院に委任することに同意し、将来〇〇寺に改葬等の必要が生じた場合、当寺院がそれを行うことに同意する。
第九条(使用権の取り消し) 略
第十条(不可抗力による事故の責任) 略
第十一条(供養方法)
永代供養は当寺院の住職が行う。
第十二条(規則に定めない事項) 略
第十三条(規則の改定) 略
資料請求の樹木葬寺院との比較
見学した永代供養墓苑とは別に、一応比較するために、岡崎市内で樹木葬式による永代供養墓の資料を請求していました。しかし実際に送られてくるまでに数日かかったのは、マイナス評価。
内容的には、
・石碑がプレート型の1人専用区画が26万4千円(以下いずれも税込)
・小さな塔型の石碑が付く1~4人用区画が、1人55万円、2人66万円、3人77万円
・個別の祭祀はなく、合祀墓区画での合祀は、11万円
一応、私たちが選択した方式の方が、費用的には少々高くつきます。しかし、外見的に見分けが付き、お花を供える
こともできるので、良かったのではと思っています。
ところで、ちょうど一昨日9月17日付け日経の<ネクストステージ>欄に、お墓選びに関する特集記事が掲載。
現在、樹木葬や納骨堂への関心高いことを紹介。
その費用について、以下の内容を記していました。
・永代供養墓は、他の人の遺骨と一緒に埋葬する合葬墓が中心で、費用は、5万円程度から
・樹木葬は、墓石代わりに木や草花を植える、合葬墓式や個別区画式などがあり、平均費用70万円
・納骨堂は、大半が屋内に置かれ、ロッカー式や自動搬送式により、平均費用84万円
樹木葬のブームは去っているのでは、と思っていたのですが、意外に根強いんですね。

自分たちの終活の一環となった永代供養機能付き「生前建墓」
2022年10月15日、生きていれば満101歳を迎えた日に、開眼供養・入魂式を納骨式を兼ねて行います。
まだ当分は生きたい私たち夫婦の名前も刻まれたお墓がデビューします。
「生前建墓」というそうです。
これにより、夫、妻どちらが先に逝っても、残された方は、お骨の処理の心配はありません。
残ったどちらかが亡くなった場合は、その対応をしなければならない息子たちも、悩むことも、どうするか考える必要もない。この同じお墓、モニュメントに骨を収めてくれればいいわけです。
もし夫婦とも2030年までに亡くなれば、契約した個別の区画でのお墓の保守期間は、33回忌を迎える32年後の2062年。
このときには、長男は88歳、二男86歳、三男82歳で、それぞれ自分たち夫婦と家族のお墓をどうするか考えてもよい年齢になっています。
私たち夫婦と(義)母は合祀墓に移され、大野家と彫られた個別墓がなくなってもなんの支障もない状況になっているわけです。
もう10年長生きしたら・・・。
そこまで考える必要はないですね。
とても良い終活の一つの課題がこの機会に解決でき、備えができたと、満足しています。
次回は、相続に関する体験がテーマです。
(以上2022年9月19日、記)

夫婦の終活を同時可能にした、二家一体の永代供養墓と生前建墓
見送りを終わって間もない日に、偶然あった永代供養墓見学会の新聞折り込みチラシ。
そこから、義母のお墓の手配と私たち夫婦自体のお墓をどうするかという終活課題の一つ。
両方を一度に解決する方法を知り、実際にそれを実現できました。
現代社会の一つの問題であり、お墓を守る人がいない、墓じまいなど、お墓をどうするかというすべての人に共通の課題。これに対して、私たちなりに先手を打って答えを出すことができた。
この事実に、今そしてこれからも安心を持ち続けることができることを嬉しく思っています。