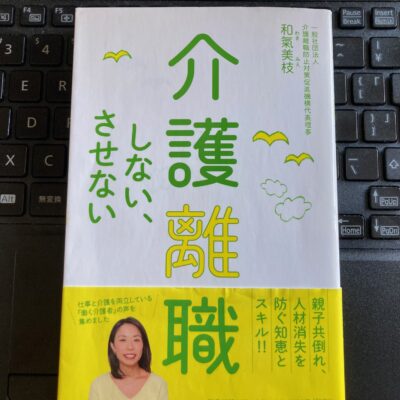100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月)
6.亡き義母名義の土地相続登記手続きに振り回される(2022/9/22)
100歳で亡くなった義母の看取り、特養からの退去・移送、納棺・直葬による葬儀、火葬・見送り、お墓対策
と進めてきました。
今回は、死去に伴い、義母名義の土地の相続のために行った諸手続きにおいての面倒な実体験を、詳しく回想
します。

シンプルなはずの相続問題も本籍変更回数多く、走り回ることに
特養での看取り、葬儀社への移送・納棺・出棺、斎場での火葬、お墓の手配、そして。
8月16日に特養での義母の看取りから火葬による見送りが終わってから、お墓の手配まで。
死後必要な対応・手続き等も一応順調に進め、8月25日頃から、もう一つ、必須の課題への取り組みを始めました。
それは、義母所有の30坪程度の土地の相続手続き。
義母保有の土地の長女(私の妻)への権利移転登記申請へ
相続する現預金はほぼ皆無で、二人の娘(私の妻とその妹)の間の相続については、唯一土地だけが課題としてありました。
義母所有の土地に、私名義で家を建て、同じ屋根の下で30有余年、生活。
90歳まで、一応現役として、生命保険会社の営業職を続けてきました。
その間、食事や洗濯など身の回りのことは、一切長女(私の妻)が行ったので、義母は家事に一切携わることなく、自分だけの生活を送っていればよかった。
そういうことから、長女と二女の間では、土地は長女が相続すると決めていました。
いずれにしても、土地の相続に関する所有権の移転登記が必要。
他の課題のほとんどが一段落ついたので、その作業に入ったのが、特養所長への最後の御礼・挨拶を終えた日の翌8月25
日(木)から。

作成すべき3つの基本書類、登記申請書・相続関係説明書・遺産分割協議書と多種の添付書類申請・収集・整理へ
相続に基づく土地の所有権移転登記には、3種類の書類の作成が必須でした。
その書式や作成法は、法務局のホームページに掲載されており、そこに提示された事例を参考に、準備を進めていきました。
(参考)⇒ 不動産登記の申請書様式について
その3種類の書類と、それらに添えるべき諸資料について、以下整理しました。
1)(所有権移転)登記申請書①
相続人が申請し、対象の土地の課税価格とその額に応じて納付が必要の<登録免許税>を記入。
次ページにその金額分の収入印紙を購入し、白紙に割り印せずに貼付②
・その基礎となる<固定資産(土地・家屋)評価証明書>④を市役所で入手が必要
2)相続関係説明書③
被相続人(死亡者)と法定の相続人との関係を示す図
※1)と2)の書面①②③④を綴じる。
※この①~④までを綴じたものに、被相続人の死去に伴う(戸籍)除籍、(住民票)除票に加え、出生から死亡まで本籍を置いたすべての自治体が発行する戸籍に関する証明書(=改製原戸籍)と相続人(妻)の戸籍謄本一式を付。
※但し原本の返還を求める場合は、それらのすべてのコピー(の裏面)と各次頁とに割り印したものを提出。
3)遺産分割協議書
相続人間で協議・決定した内容を文書化し、署名と実印押印。
※この協議書に、相続人(妻)の住民票・印鑑証明書と、長女の単独相続に同意した二女(妹)の住民票・印鑑証明書を添付。
この3種類の資料に、上記のように付け加えた自治体発行の証明書類を入手し、添付することになります。
但し、この記事を書いている時点で、法務局にコピーと原本のすべてを提出してしまっており、添付書類の割り振りに違いがあるかもしれません。
返還された資料をもとに、間違いがれば後日訂正いたします。ご容赦ください。

被相続人(義母)の戸籍関連証明資料入手の顛末
長女・二女の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は、なんの問題もなく取得できたのですが、問題は、(義)母の戸籍関連証明書類です。
厄介な<出生から死亡までの戸籍>(改製原戸籍)等の入手
まず、死亡した被相続人(義母)の出生から死亡までの戸籍と死亡時の住民票が必要。
そのため、8月26日(金)に岡崎市役所の支所に赴き、・戸籍の除籍謄本 ・住民票の除票等を発行してもらったところ、死亡時の現住所と同一の岡崎市を本籍とした「改製原戸籍」の発行を受ける。
そこで、岡崎市の前にあった愛知県高浜市の戸籍記録(=改製原戸籍)と出生地である岐阜県武儀郡の戸籍謄本(=改製原戸籍)が必要になるとの助言。
取り敢えず高浜市での戸籍を取れば、出生地の岐阜県武儀郡の戸籍の次の戸籍の有無と内容がわかるはずと。
率直なところ、死亡時と出生児の戸籍が確認されれば、相続要件を確認する上で十分ではないのか、と思うのだが、こういう決め事は、従うしかない。
岡崎市で発行してもらった<改製原戸籍>に、相続する妻(=義母の長女)の出生届けが行われた記録があり、それが碧南市内の地名で示されていたので、そこにも義母が戸籍を置いた地かもしれない。
では、これらの市役所の戸籍担当部署にどのようにして発行を依頼し、集めるか?

<郵送での戸籍証明等交付申請書>を3市の戸籍担当に郵送とその対応への再対応
岐阜県や、近いとはいえ高浜市、碧南市に直接それらの証明書類を取りに行くべきかどうかを調べてみた。
各自治体ホームページに、郵送で申請を受け付ける旨案内があったので、まずは、この方法でやってみることに。
但し、武儀郡は既になく、美濃市に併合されており、美濃市・碧南市・高浜市の3市に、戸籍謄本発行手数料450円分の定額小為替と切手貼付返信用封筒、それに、手数料が不足する場合はメールで連絡頂ければ、即不足分の定額小為替を郵送する旨の書面を添え、申請書を8月29日(月)に投函。
少しばかり不安を感じつつ待つと、8月31日(水)に、美濃市のご担当から、<改製原戸籍>2通発行により1,050円不足のメールでの連絡。
すぐに不足分の定額小為替を求めて郵送。
同日、碧南市のご担当からは、参考のために同封した改製原戸籍に記述があった碧南市の所在地では、該当する本籍地のものが見つからなかったと連絡。
従い、その時点でまだ分かっていない美濃市及び高浜市発行の戸籍関係原簿を入手した結果・内容を見た上で連絡する依頼。
翌9月1日(木)に、高浜市のご担当から美濃市のケースと同様に、改製原戸籍2通発行することになるため、1,050円不足と、夕刻、メールで連絡受け。
同日中の不足額の定額小為替発行と郵送は、時間的に不可能で、翌9月2日(金)午前中手配し投函。
週が代わり、9月7日(水)美濃市より分厚い2種類の改製原戸籍が届く。
ご先祖が大家族構成で、1件ごとの枚数が多く、郵送料金56円不足で、別途所定はがきに切手貼付して投函。
翌8日(木)高浜市より同様2種類の改製原戸籍が届き、こちらは郵便料金不足発生せず。
双方の内容から、碧南市に本籍を置いていたことが読み取れ、すぐに碧南市のご担当に電話を入れて、表示されていた本籍地を伝え、すぐ調べてもらう。すると、間違いなくあり、同様2通で1,500円になるとのことで、一旦、先の2市同様不足分を郵送する旨伝え、対応を依頼。
しかし、想定よりも日数を要しており、郵送にすると、またまた翌週になってしまうので、妻と話し合い、翌日直接碧南市役所に行き、発行してもらう旨、即電話。
ご担当が、「では用意しておきます。お気をつけてお越しください」という丁寧な、感じの良い対応。
そして翌日、ドライブがてら碧南市役所へ。
電話でのご担当は他業務で不在でしたが(残念!)、郵送しておいた定額小為替と切手貼付の返信用封筒を返却してもらい帰宅。
ようやく、これで必要なものはすべて揃い、申請する準備に入ることに。
定額小為替決済の不便さと発行手数料の高さ
ここで、本筋から離れますが、自治体に納める発行手数料の定額小為替による納付という規定。
今どきなんだ!と。
450円の定額小為替1枚の発行手数料が200円。
追加の1050円分では、額面1050円というものはなく、2枚に分ける必要があり、合計手数料が400円。
実質的にこれは送金手数料に当たるわけで、インターネット時代において送金手数料が引き下げられる傾向にあることを考えると無茶苦茶。
こんな事がいつまで続くのか、行政システムの遅れを象徴するもの。
デジタル庁の改革課題の中に、多分入るわけないでしょうね。
法務局での登記申請に関する<手続き案内>予約と相談
一応、全く価値を生まない、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の行方の探索作業を終え、提出すべき資料が揃いました。
その内容や資料の綴じ方・順序が適切かどうかなどを、事前に法務局に相談し、問題や不備が発生して、訂正や資料の追加などが必要になることがないように。
そのためには、<登記申請に関する手続き案内>を受けることが可能だが、そのためには予約が必要と。
その手続き案内資料には、「申請内容の適合性や登記の完了を保証するものはなく、申請前の書類の不備(添付書類や記載内容の確認等)について決して事前の審査は行わない」と。
しかも1回の手続き案内のための時間は20分以内だと。
なんというお役所仕事、上から目線、責任回避型業務。
仕方なく、9月12日14時の予約をとり、相続人であり申請者である妻と名古屋法務局岡崎支局へ。
相当のボリュームの資料一式をパラパラめくりながら確認。
手慣れた流れに沿って、戸籍関連資料等の返還を前提として、資料を並べる順番、綴じ方・セットの仕方、コピー書類への割印等、一気にまくし立てられて、それが整ったら申請窓口にこれを持参して申請を。
渡された「これ」とは、9月30日が登記完了予定日とされた「登記完了予定表票」。
翌10月1日・2日が土日なので、10月3日以降に完了確認と提出済みで返還を求めた諸証明書類の受け取りに来局をと。
一生懸命理解し、忘れないように、間違わないようにと、担当官がやってくれた資料一式の整備・提出法そのままを重ね、同局内で、貼付用印紙2万3,100円分も購入して帰宅。
あってほしくなかった書類不備による要「補正」連絡により名古屋市東区役所へ出向く
少しばかり不安があったが、12日(月)に戻って後、翌13日(火)に、義妹(相続人である妻の妹)に会って、すべての提出資料一式を説明し「遺産分割協議書」への署名・実印捺印を依頼。
これで必要書類すべて揃ったとして、14日(水)最終提出書類を整理し、作成・完了。
翌15日(木)法務局に提出。
少しばかり提出の仕方に不安があり、30日まではなんの連絡もないようにと祈っていたのだが。
平日・週末・祝日と4日間を経過した20日(火)夕刻、担当官から、被相続人の出生から死亡までの改製原戸籍に1ヶ所、名古屋市東区を本籍とする部分が欠落しているという指摘。
12日の手続き案内時には担当官からは指摘されなかったものであり、なんのための時間だったのかガックリ。
が、先述のように、当初から責任回避をアピールしている手続き案内。
黙って対応するしかなく、翌21日(水)、先の碧南市役所に直接赴いたのと同様、名古屋高速も使って名古屋市東区役所へ赴き、改製原戸籍1通を入手。
すぐさまとって返して、名古屋法務局岡崎支局へ行き、その書類を確認してもらい提出。
一応、翌日対応したので、当初の予定通り、月内登記完了されるか尋ねたところ、ほぼ大丈夫と。
相続に必要な諸手続きは、司法書士などの専門家を利用せず、当初から妻の代わりに私がすべて行い、件の手続き案内と登記申請等では、妻が必ず同行するとして取り組んだもの。
良い経験にはなりましたが、結局、準備開始から正式な登記申請まで、要した日数はほぼ1ヶ月近く。
それにしても随分振り回されました。
義母のファミリーヒストリーの一端を知ることに
100歳で亡くなった義母は大正10年生まれ。
岐阜県で生まれた頃は、当然家父長制が色濃く、生家の戸籍も随分賑やか。
子だくさんなのはご多分に漏れずでしたが、意外に離婚・離縁が多く、義母も一時期、長男である兄の戸籍に入っていたり、未婚の母の状態であったり、離婚しシングルマザーであったりと多彩?
初めて耳にし、目にした改製原戸籍から、いろいろなドラマが想像・想定されました。
しかし、相続をめぐり、そうした情報とそのための書類の大半は無用のもの。
今回の作業では、残念ながら厳しい言い方をすると、余計な時間と労力とコストの負担を強いられたと感じざるを得ませんでした。
行政システム及び関連法制の抜本的大改革を10年かけて!
こうしたことから、今回の相続問題で、行政手続きが複雑化し、そのまま形式化していることを体験。
繰り返しになりますが、それにより、必要ない費用を負担し、時間を要し、各種証明書の発行に市役所職員や法務局担当者の時間と労力、すなわちコストをも随分発生させている行政事務システム。
相続に関する権利移転登記に限らず、こうした行政上合理化・効率化すべき課題は、相当残っている。
10年間くらいかけて、デジタル化・ネットワーク化を軸にして、関連法制と業務システムを大改革すべきとかねてから思っています。
さて、10月初旬法務局に出向き、妻への土地相続が無事確認できれば、私の役割の一つが達成されたことに。
今後に役に立つ経験ができたと感じています。
この相続対策。
終活においては、ある意味最も問題になる案件であり、生きているうちから対策・対応を考えておくべきと再確認した次第です。
今時の例は、最もシンプルな形のものだった気がするのですが、しかし戸籍問題には振り回されました。
同様の問題が発生しそうな方は、終活の一環として、戸籍・本籍の移転について、今から調べて置くことをお薦めします。
私たち夫婦も、それぞれのこれまでの本籍の変遷は、しっかり確認することになりました。
次回は、社会保険関係の諸届け等について簡単に報告したいと思います。
(以上2022年9月22日、記)
土地建物の相続手続きをしない要因と相続登記義務化実現
親の死後、土地建物の相続を法律に則って行わないことで、全国で放置された空き家が増え続けている。ここ10年以上問題になってきました。
その最大の要因は、間違いなく相続税にあると思います。
しかし、この相続手続きの煩雑さも、同レベルで大きな要素を占めると確認。これが今回の義母所有の土地の相続をめぐる体験でした。
今回の例は、空き家空き地問題とは根本的に異なる相続問題ですが、上記の回想記を読めば読むほど、バカバカしくなります。
ようやく政府も重い腰を上げ、その改善に取り組むべく法改正が実現しました。
今年2024年(令和6年)4月1日から相続登記を義務化する法律が施行されています。
当然遵守しない場合の罰則が規定・強化されたわけです。
(この法律については別途終活テーマの中で紹介する予定です。)
限られた資源の代表ともいえる土地不動産。
その有効活用は本来国民全員が共通してもつべき国としての方針・政策と思いますが、決して罰則規定を強化してその対策に当てる方法は、目的と手段をはき違えているものといえます。
法改正を行うからには、私が経験した上記のようなムダやムリをなくし、方法を簡素化する改正もセットで行うべきでしょう。
相続手続することがなんの苦も無く、むしろ進んで行うようになるような相続法改革に踏み込むべきと考えます。