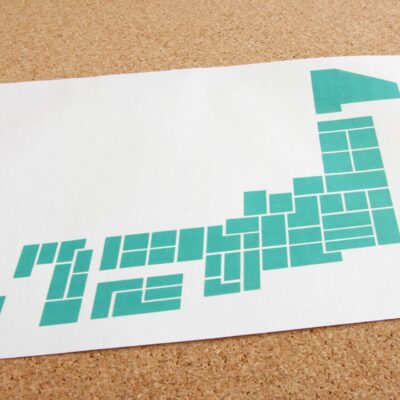100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月)
2.特養生活の100歳義母を看取り、見送った1ヶ月(2022/9/16)
介護、お葬式・火葬、お墓、相続、納骨等終活関連体験記を
昨年10月に、特養入所中の義母が100歳を迎えたことを前回の記事で報告しました。
⇒ 98歳義母「特養」介護体験記|コロナ禍の特養介護生活と2介護施設での費用を11記事で回想 – 介護終活.com
あれからほぼ10ヶ月の8月10日から、入所する特養での介護が「看取り介護」の状況・態勢に。
それから間もなく、8月16日夜に同所で看取り。
事前に打ち合わせてあった葬儀社に連絡を取り、翌日17日午前中に引き取って葬儀社の安置室に移送。
同夜形式的な通夜を済ませ、無宗教式の直葬式で、翌18日火葬と骨上げ。
翌19日の特養退所手続きに始まり、同退所・引き払い、市役所・年金事務所等社会保険関係手続きに。
お骨・お墓をどうするかの検討により永代供養墓の手配・契約。
私の妻である長女と二女の相続に関する諸手続きを経て、昨日9月15日に法務局への土地所有権移転登記申請書提出。
この他、義母の預金口座の解約等の手続きはありますが、義母が生きていれば満101歳を迎えたはずの来月
10月15日に、開眼供養入魂式を予定。
他に、年内に喪中の欠礼はがきを手配することを残してはいますが、一応、今日で逝去後1ヶ月と一区切り。
この1ヶ月余、70歳台の私たち夫婦の近い将来を考える上で、非常に良い経験をできたと思います。
そこで、このフェーズでは、以下のようなテーマで、種々の経験を振り返り、考えたことなどを整理します。
1)介護:特養における看取り介護サービス、看取り体験と介護保険制度について
2)お葬式:契約葬儀社による葬儀方式・葬儀サービス・葬儀代等について
3)見送り:火葬・骨上げなど火葬場での一日について
4)お墓:永代供養方式によるお墓の手配と契約、納骨及び管理方法、納骨式等について
5)公的諸手続き:死亡者の社会保険等諸手続き等について
6)相続:相続問題対応と不動産所有権移転登記諸手続き等について
7)老後費用:老人施設利用による老後諸費用などの実態等について
8)生き方と終活:終活のあり方、世代の役割等、看取り・見送りをめぐる経験からの総括
9)永代供養墓納骨・供養:終活の総括ともいえる納骨と永代供養等について
人生を一つの視点から凝縮した1ヶ月有余の経験。
10月15日までの2ヶ月間で、ある意味完結をみたわけです。
視点を変えれば、これからの私たち夫婦自身の終活とエンディングのあり方を真剣に、現実的に考え、準備を開始するきっかけになりました。その一部をこの機会を利用して紹介します。
例えば、葬式をできるだけ安く行なった方法や永代供養墓の生前建立などを含みます。
なお、次回には、特養での看取り介護と、実際の看取りから施設からの送り出しと退所手続きなどの体験を、介護保
険制度についても一部触れながら思い起こしてメモすることにします。
(以上2022年9月16日、記)

義母死去に伴う必須事項、初めから終わりまでの終活事情
93歳から100歳までサ高住と特養で生活を送っていた義母の介護と施設介護でしたから、一般的な終活とは意味合いが違うかもしれません。
しかし、体験した一連のプロセスをたどると、共通点は多くありますし、何より自分たち夫婦のこれからの終活を考える上では、参考になります。
それは同時に、一つの例として、多くの方々にとっても参考やヒントになるのではとも思っています。
そのいくつかは、そしてまた多くは、これからの日常生活において準備が可能なことと考えます。
介護への備え=介活と、人生の最期への備え=終活は、かなりの部分で関連し、一部重なりあっていて、すべての人に共通する課題です。
今回の終活体験回想記の<第3フェーズ>が終わりましたら、一般論としての介活と終活に関しての提案も、できればシリーズ化していく予定です。