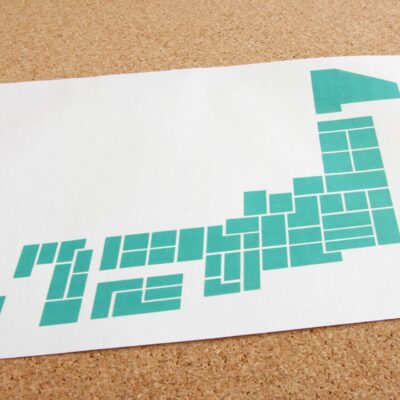100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月)
10.100歳逝去義母の101歳誕生日10月15日、永代供養墓・開眼供養入魂式営む(2022/10/15)
92歳でサ高住に入所。2020年5月に特養に転所して昨年満100歳を迎え、101歳直前で老衰のため逝去した義母。
これまでの経過等を、ここまで9回にわたり回想してきました。
親での体験・経験は、自分自身の終活の予行演習。
しっかりと刻むことができたと懐かしんでいます。
特養で満100歳を祝って頂いた翌年2022年6月頃から食が一気に細くなり、意識が戻りにくく。8月急速に老衰が進行し、16日静
かに息を引き取りました。
9月19日の敬老の日まで1ヶ月余、10月15日の満101歳まであと2ヶ月。
もう少しのところでしたが、最期の看取り介護をしっかりやって頂き、二人の娘夫婦共々看取ることができました。

種々の対応で慌ただしく過ぎていった9月でしたが、10月に残っていた一大イベント。
それは、生きていれば満101歳の誕生日だった今日、10月15日に予定していた義母の納骨。
幸い良い天気に恵まれ、永代供養を行なって頂ける寺院のご住職を迎えて、滞りなく終えることができました。

土地所有権相続登記完了と「登記識別情報通知」を受け取り
その前に、今月もう一つの重要事項の処理がありました。
それは、いろいろ時間と労力とコストを要し、かつ補正も必要だった義母が残したわずかな土地の所有権の、妻への相続登記の完了確認。
設定されていた登記完了予定日10月3日に、名古屋法務局岡崎支局へ。そこで、「登記完了証」と以前の<土地権利証>に当たる「登記識別情報通知」、及び返還を申請していた各種登記簿や証明書類の原本を受け取って一安心。
それ以外の細かい事務的な事項には以下がありました。
・先に8月分として徴収されていた後期高齢者医療保険料と介護保険料の過納部分の入金
・高額介護負担料の返還部分の相続人である妻の銀行口座への返却手続きと入金確認
・土地所有権移転に伴い、新たにその固定資産税および都市計画税の負担者に対する同税の請求に基づく支払い方法の届出は、登記完了通知が法務局から市の固定資産税担当部門に送達。それに基づいて市の担当課から後に行う
ということでした。


満101歳の誕生日に、義母の納骨式に当たる<開眼供養入魂式>を営む
こうして、何とか101歳を迎えられないかと願っていた今日10月15日。
一応、一般的には49日を過ぎてから納骨をということで、永代供養を契約したお寺のご住職に、この日を選び、<開眼供養入魂式>を営んで頂きました。
昨日に続く、真夏に戻ったかと思われる強い日差しの炎天下、厳かに上げて頂いたお経と講話のなんとも言えぬ響きが、仏教徒ではない私にも心の安らぎをもたらしてくれ、素晴らしいひとときとなりました。

私たち夫婦の永久供養墓を生前建立
今日のこの日を、逝去した義母の見送りのための諸事万端の一つの目標地点・目標時点としてきており、務め・役割を終えてほっとしています。
こうして種々経験できたのですが、私たち夫婦の終活を考える機会となったことに加え、私たち夫婦の永久供養墓の生前建立を兼ねることになり、究極の終活そのものを実践したことになったこと、多としたいと思います。
(以上2022年10月15日、記)

当サイト運営目的の実践と提案に向けて
元々は、合計35回にわたって義母の介護と看取り・見送り体験を回想記として綴ってきたシリーズ。
これを、サイトの再開を機に、3つのフェーズに整理し、1フェーズ1記事として投稿。
その第3フェーズが、本稿でした。
これまで何度も繰り返してきましたが、超高齢化社会において、介護問題はほとんどすべての人々に関わる困難な課題です。
基本的には、国と自治体による介護行政・介護保険制度に基づいて運用・管理されていく介護制度。
ともすれば、介護財政を維持することを第一義として議論され続けています。
また、いまもなお増加を続けている介護離職が経済的な損失を招くゆえ防止すべき。
この視点で議論される傾向も、未だに顕著です。
しかし、その方向性は、財政問題ではなく、むしろ企業サイドに負担の矛先を向けると同時に、現役世代と高齢世代双方の経済的負担が増すこともやむを得ないと、矛盾を強いるものです。
介護保険制度、介護問題の改善・改革に根本的に取り組むものではなく、すべては問題解決の先送りを繰り返し続けていることは、制度開始以来まったく変わっていません。
そのため、当サイトではそれらの制度問題に対する改善・改革を提案することを厭いません。
しかし、そうしたいびつな制度を前提として、どのような対策・対応をとるか、自衛する観点からの検討・考察そして提案に力を入れていきたいと考えています。
自衛策は、介護する人される人、どちらにとってもより望ましい介護生活・高齢者生活、そしてもちろん現役世代生活を送るためのものです。
フェーズごとの3つの記事。
どれも非常に長い記事であり、読みずらい、分かりにくいものだったかと思います。
お付き合い頂きまして、ありがとうございました。
昨年、開設し、運営してきた元のサイトでは、全部で約120の記事を投稿していました。
その中に、「介護離職」防止対策と「終活」実践法のシリーズが含まれていました。
この2つのシリーズも記事数が非常に多かったのです。
そのシリーズも、今回の体験記のように、1記事に、元の複数の記事をまとめて、再編集し、投稿する予定です。
もちろん、本来は、今リアルに問題となっていることや、今提案しておきたいことなどを、積極的に取り上げていくことが目的。
有益な情報提供も交えていきます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。