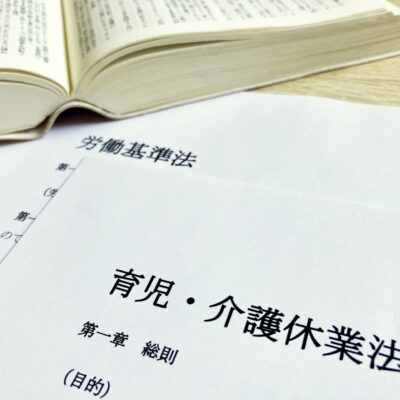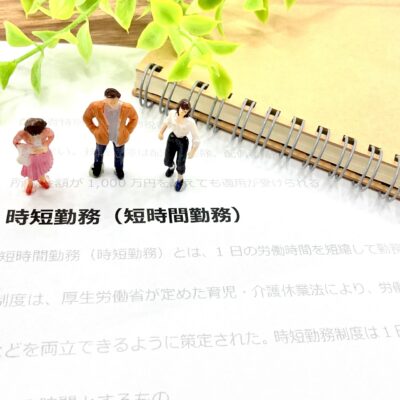100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月)
100歳義母看取り・見送り体験記<第3フェーズ:終活完遂期>(2022年7月12日~2022年10月15日)
近づく100歳義母の死期。家族葬か直葬か
一昨年2022年8月に、生活を送っていた特養で100歳で逝去した義母。
2015年から5年間のサービス付き高齢者住宅での生活と2020年からの特養での生活を回想した2つのシリーズ
・『93歳義母介護体験記<第1フェーズ:サービス付き高齢者住宅(サ高住)介護期>シリーズ』
・『98歳義母介護体験記<第2フェーズ:特別養護老人ホーム(特養)介護期>シリーズ』
を終えています。
どちらも、14及び11に及んだ投稿回数の記事を、一つにまとめています。
⇒ 93歳義母「サ高住」介護体験記|2015年の記録と気づき – 介護終活.com
⇒ 98歳義母「特養」介護体験記|コロナ禍の特養介護生活と2介護施設での費用を11記事で回想 – 介護終活.com
今回は、介護及び終活体験記最後の段階。
『100歳義母看取り・見送り体験記<第3フェーズ:終活完遂期>』シリーズの10記事を一つにまとめました。
義母に対する介護終活体験の総括に充てたいと思います。
当シリーズでの10の回想記事の構成は、以下です。
タイトルを一部修正している場合もあります。
『100歳義母看取り・見送り体験記<第3フェーズ:終活完遂期>シリーズ記事リスト』
1.近づく義母の死期、見送りの備えを(2022/7/12)
2.特養入所の100歳の義母を看取り、見送った1ヶ月(2022/9/16)
3.特養での看取り介護から看取り、お別れ・退居まで(2022/9/17)
4.葬儀場安置室移送、直葬式、火葬・骨上げ帰宅まで(2022/9/18)
5.永代供養墓の契約は私たちの終活を兼ねて(2022/9/19)
6.シンプルなはずの相続問題も戸籍変更回数多く、走り回ることに(2022/9/22)
7.社会保険関係諸手続きで故人の社会との関係消滅を実感(2022/9/23)
8.92歳時老後資金1千万円、100歳看取りで残高ゼロに(2022/9/25)
9.世代を引き継ぐ看取り・見送り、自身の終活を考える機会(2022/9/26)
10.故人101歳誕生日10月15日、永代供養墓・開眼供養入魂式を営む(2022/10/15)

ページに広告が含まれます。
1.近づく義母の死期、見送りの備えを(2022/7/12)
死んでもかかる消費税。家族葬、直葬しっかり事前検討を
特養で暮らしている100歳超の義母が、先月から少しの時間、意識がなくなったりすることが増えてきています。
看取るべきが近づきつつあるようです。
そこで、葬儀の準備も必要かと、今月7月初めに4年前に入会した葬儀社に相談に行き、説明と提案を受けました。
これを受けて、同社のシステムにあった必要費用の一部を生前予約金として納付しておくことを妻(義母の長女)と決め、先日申込みに。
最近は、葬儀業界の競争が激しく、1週間に何度だろう、各社の折込チラシが入る。
入会金の割引とか、携帯電話のように他社からの乗り換え割引とか、事前相談会参加時のクーポン等配布とか。
ところで、あまり深く考えていなかったが、実は葬儀費用には消費税がかかることに気がついた。
そうなんだ。
死んでも消費税がかかるんだ!
なんとも不思議な感覚・・・。
最近は、コロナ禍の影響が大きく、もっぱら家族葬という小規模な葬儀が主流。
しかし、この家族葬もうっかりするとかなりの額になる。
広告上の、「○○万円~」の「~」が問題である。
そこで提示提案された金額は、当初イメージしていたものよりも、いろいろ条件加算が積み上げられて、相当額にあっという間になる。
その上での消費税である。
ただ基本的に、標準としての家族葬は、仏教式を前提としている。それが一般的・常識的という固定観念に従えばやむを得ない額。
そういう気になってしまう。あるいは、そういう気にさせられてしまう。
日常生活において仏教にはほとんど全く関係なくても、葬儀や家族が亡くなると急に仏教式に倣う。
否定してはいけないと思うが、疑問は残ったまま。
ところで当事者である義母。
幸か不幸か、信仰心のない人。私たちも無宗教なので、葬儀は仏教式をなくして行う方法でと依頼。それを前提にして説明・提案をうけた。
親戚関係は二人の娘とその家族のみで、一般的な「家族葬」レベルではない「直葬」という方式。
ごく少数の近い親族・家族に限った、最小規模の葬儀というわけだ。
仏教式を前提とした家族葬では、広告のうたい文句では、30万円台でできるような感じだ。しかし、恐らくとても
とてもムリではないかと、説明を受けて感じた。
不明朗な部分も多いが、付加的事項がいとも簡単に膨れ上がるシステムといえるだろう。50万円くらいにはあっという間に到達しそうな感じである。
よほど心して、きめ細かく質問し、説明を受けておかないとまずいと思う。
そして、今日、コロナで長く面会が禁じられている中、先に示されていた、2週間分の体温測定記録を持参するという厳しい条件。これをクリアして、妻とその妹と私で義母の面会に。
面会後、特養サイドに、看取り時の対応や、葬儀社への引き渡しなどの流れについてまず話を伺った。そのうえで、現状もってい
る不安や疑問点などについて、確認してきた。
ということで、いざというときの備えが多少はできている。
また今日、葬儀社から今月初めの相談へのお礼として、QUOカードと、葬儀時利用可能な割引券などが郵送されてきた。
もらえると思っておらず、競争の激しさを示す一端といえる。
割引券は、一定額以上の家族葬でしか利用できないので、使うことはないだろうが。
その義母。
つい先だって100歳を迎えたところ、という感覚だったが、もう3ヶ月余で、満101歳。
見る限り、100歳には見えないが、認知度もかなり低下してはいる。
特養という恵まれた環境で、止まったままの時間を過ごしている。
(以上2022年7月12日、記)

お勧めしたい葬儀の事前相談
4年前に、自宅から近いということと、新しく建てられた施設という2つの要素から入会した葬儀社。
そろそろ義母の葬儀を具体的にどうするか、妻と話し合っておく必要があるとかねてから考えていました。
また100歳を超えたこともあり、契約した葬儀社に相談しておくのがよいと、予約をとって出向いたおりの経験です。
団塊の世代全員が後期高齢者となる今年度。
その親の介護と看取りを既に経験した人も多いと思います。しかし、これからは自分自身が介護を受け、あるいは看取り、見送られる番になるわけです。
どちらの立場であろうと、葬儀・葬送は避けて通れない終活最大のイベント。
折り込みチラシ、TV広告、ネット広告、そして道すがら目にする林立する葬儀社の露出度の激しいこと。
エスカレートする一方です。
ついつい気が向くのは、やはりその費用。
家族葬といっても、それなりの額が示されています。決してそれがこじんまりとした葬儀を想像させるような額ではないと思います。
やはり、実際に葬儀社に直接相談し、種々話を聞いてみるべき。
最後の回想記シリーズでは、義母の介護ではなく、義母の人生の最終章について私たちが担当した終活体験の回想になります。
これは、私たち夫婦自身のこれからの終活に活かすことができるもので、回想にも意味があると思いつつ取り組んでいきます。