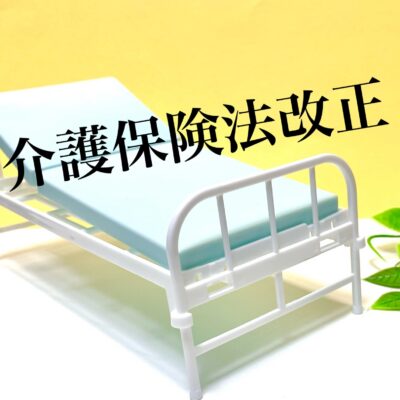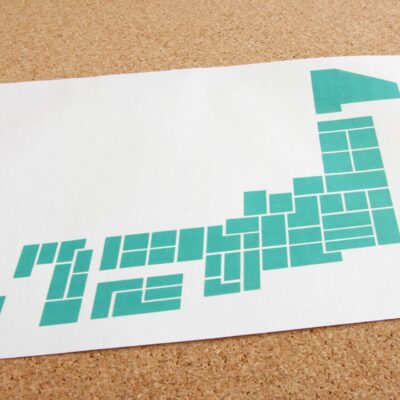93歳義母「サ高住」介護体験記|2015年の記録と気づき
8.介護拒絶する要介護家族と介護者のすれ違い|親子間コミュニケーションの難しさ
2014年、義母の左脚大腿骨骨折・入院・手術。・リハビリ開始、と想定された順序で進んできた義母の病院生活。
翌2015年、急性期病院から回復期病院への転院そしてリハビリが進められ、病院からの急な退院要請。
急遽介護施設探しと見学を行い、義母の入所先としてサ高住を選択。
要介護認定申請により<要介護1>の審査結果を受け取ったのですが、問題は、義母の入所拒絶。
退院期限も迫ってくる日々の回想です。
介護施設入所拒絶の要介護家族と介護者のすれ違い(2015/3/12)
昨年12月上旬の骨折→中旬手術→1月リハビリ転院→1月下旬要介護認定→2月上旬介護施設決定、と、義母の介護が自宅では困難になったことから複雑な思いで、夫婦で話し合いながら進めてきたのですが。
これまでのプロセスで、義母本人は当初から一貫して、「デイサービスは受けない、施設には絶対入らない、家に帰る、世話にならないで全部自分でできる」と主張を続けるばかり・・・。
非常に気丈な性格で、今までの暮らしでも、娘と張り合うような、娘に対して威張るような言動を続けてきたことからも当然予想できたことでしたが・・・。
2月の半ばに。心身共に不安定さが昂じる妻にはムリなので、入院先の担当介護支援専門員さんにお願いして応接室を手配して頂き、義母と私と二人だけで話す機会を持ちました。
自宅で迎え入れて介護することが、娘(私の妻)の心身の健康上とてもムリなことと介護施設に入ってもらいたい旨話しましたが、想定通り、取り付く島もない態度、言葉・・・。
しかし、その後、2~3日置きに着替えを持っていく折には、特に施設云々の話は、どちらからもしない状況が続きました。
2月下旬に入所を決め、その施設に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)さんが、3月に入ってすぐに入院先に出向き、義母と面談。
面談直後に、面談の状況を伺うため、病院内の喫茶店でお会いしました。
会った直後の開口一番、義母が「絶対に施設には入らない」と言ったとのことで、本人の気持ちがそうであることを前もってお伝えしてはあったのですが。
やはり、難しさをお感じになったようです。
その面談を受けて、施設側で面談結果を元に、受け入れについて会議を開き、決まり次第連絡頂けることになりました。
(以上2015年3月12日、記)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
想定すべき介護をめぐる親子間コミュニケーション問題
老齢の親が自宅での介護を希望するのはいわば普通のこと。
介護を求められる子どもの年齢・年代や子自身の家族の事情・状況、そして仕事の状況など一括りで親子の関係といっても、人それぞれ、親子関係それぞれ、家族関係それぞれ、同じ状況などありえません。
画一的に考えること自体無理があります。
妻と母親との関係、私たち夫婦と(義)母との親子関係、そして私たち夫婦の関係、その括りでの事情・状況は、他の方々と同じものはあり得ないわけです。
ですから、介護をめぐる親子間のコミュニケーションの必要性・重要性を主張しても、簡単に、あるべき論で片づけることは無責任でしょう。
義母の介護をめぐる私たちの思い・希望と義母の考え・希望との違いは、やむを得ないもの、コトであり、いずれにしてもどちらかの意に沿わない結果になることは明らかでした。
このときの私の判断は、妻と義母のどちらの意向・希望をとるかの判断であり、実は初めに結論ありきであったわけです。
判断の前提は、「妻を守る」にありました。
そして、その結論に沿って強引にでも、義母に嫌われてでも話を進めるという意志に従っての行動あるのみだったのです。
ただ、私たちの思いは少しでも理解してもらうべく、娘の幸せも考えてもらいたい、あるいは過去の母子の関係、私たちとの同居以来の生活なども振り返ってもらいたい旨をも話しました。
直接、娘(妻)の口からは話しにくいことですが、あるいは口に出せないことゆえに、私が話し、伝えたわけです。