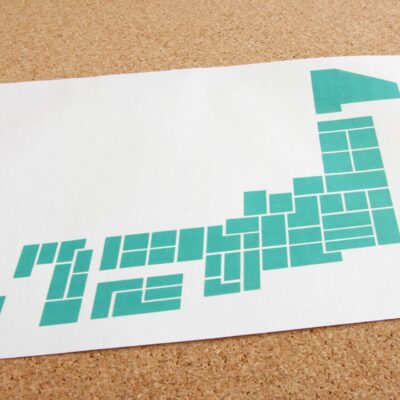93歳義母「サ高住」介護体験記|2015年の記録と気づき
4.自宅介護対応不安と介護施設検討の矛盾を抱えて|介護施設情報収集は常日頃から
左脚大腿骨骨折・入院・手術・リハビリ開始、と想定された順序で進んできた義母の病院生活。
地域包括ケア連携による「急性期病院」から「回復期病院」への転院・受け入れにより、リハビリが進められましたが、退院後の在り方について不安が募った経験を今回回想します
自宅介護準備と介護施設検討の矛盾を抱えて(2015/3/1)
認定調査が終わり、リハビリも進む中、義母の「家に帰りたい」という気持ちが日に日に強まっていきました。
リハビリに最適の環境で、日に日に回復し、人の手を借りずに自分でナンでもできると自信を深めていっている感じ・・・。
しかし、入院前は、というよりもこの30数年間は、娘(妻)にほとんどの家事をやってもらい自分のことだけをやっていれば良かった。
その義母も、90歳を超えてからは少しずつ体がいうことをきかなくなり、種々不安・心配事が増えつつある中、(当時)60歳代後半の長女(妻)がカバーしている上でのことをまったく感じていない。
自宅介護可能を目標とした回復期リハビリ方針と自宅復帰準備
病院側も、自宅に戻ることを想定して、玄関や家の中の階段・段差の有無・高さ、部屋の入口や廊下の幅、手すりの有無、間取り・構成、トイレ・浴槽の作り、居室・寝室の状況等自宅の生活環境と諸条件を病院専用のデジカメで撮影し、所定の書類に計測・記入するよう求めてきました。
「◯◯回復期リハビリテーション病棟では、入院時より患者さまのご自宅での生活を想定したリハビリテーションを心がけています。患者さま宅の生活環境の情報をご提供いただくことことにより、きめ細かなリハビリテーション治療方針を検討させていただきます。」という文面で、作業療法士さん名で、撮影と書類提出要請がありました。
※以下は、不鮮明ですがその一部で、画像部分は用紙に元々あるサンプル写真です。

老々介護の問題:親の介護をする家族の健康不安
義母の骨折入院から、すぐに妻の気持ちに不安が生じ、日々増幅するようになっていました。
子どものときからの親子関係のあり方が根底にあるのですが、それに加え、自身の健康にも不安を抱えていたこともそれに輪を掛けていました。
1月に入って、種々の心配が体の不調をもたらし、不安が強くなったので、義母が入院する病院の整形外科で、妻自身が診察と検査を受け、脊椎すべり症と脊柱管狭窄症の診断。
医師からは、親の介護には支障があり、悪化すると手術の必要もあると言われ、かなりショックを受けました。
こうした状況は、老々介護にまつわる問題として往々にあることと思います。
このことで、私たちとしては、母の自宅介護はムリと判断。
なんとか、母には介護施設に入ってもらうしかないと考え、まずは、ネットで介護施設を調べ、資料の取り寄せを始めました。
そして並行して、自宅へ戻っての介護はムリで、介護施設への入所が私たちの考えであることを病院の介護相談員と作業療法士の方に事情を含めて説明。
回復期リハビリの終了目処と退院勧告で、短期間で介護施設探しを
実は、そうこうする間の2月上旬に、病院スタッフが把握できない状況で、義母が院内で転んだと連絡がありました。
大したことがなく、ありうることと私たちもさして気にすることもなかったのですが、病院としてはそうした事故はあってはいけないことだったのでしょう・・・。
元気で自分で動いている老人がちょっとした事でまた怪我をするリスク。
これは、恵まれた環境の病院や介護施設でもありうることですし、自宅で老々介護を余儀なくされる場合は、その心配から、かなりストレスがかかることは明らかです。
病院としてはこの一件で、できるだけ早く退院してほしいと考えたのでは、と勝手に推測しています。
(事実、何かあれば、病院や施設の責任を問われることが多い、と聞きました。)
もともと、転院から2ヶ月間程度のリハビリ入院期間を目標としていたのですが、1月7日の転院から2ヶ月も経たない2月末を目処としての退院をと、残すところ2週間ほどのタイミングで示唆されました。
入院している病院が複数経営する<老人保健施設>(老健)への入所も、欠員がないためか、必要なリハビリは終えているから受け入れる必要なしという判断なのか、提案・推奨はありませんでした。
こうなると、義母の思いは別として、早急に施設をなんとか探さなければいけない状態に。
この間、妻の心身の不安は、益々昂じていきました。
2週間の内に受け入れ先探しと、義母への説明・説得をなんとかしなければならない。
それまでに入手していた資料を元に、施設見学から決定など、ぎりぎりでのスケジューリングを頭で組み立てました。
(以上2015年3月1日、記)

----------------------------------
介護施設情報収集は、常日頃から
2週間以内に介護施設を決定し、義母を説得する。
今考えても、とてつもない難題を突き付けられたわけで、なんとか乗り越えることができたのは、運がよかったとしか言いようがないと思います。
施設に入れるかどうか分からない状況で義母を説得することは、到底、ムリがありました。
加えて、介護認定申込み手続きはすぐに行いましたが、どう評価認定されるかも不明。
まして、リハビリが順調に進み、要介護認定は絶対といってよいほどムリ、と推測されたことで、比較的低料金で利用できる特養への入所は、制度的にムリ。
結局民間の比較的高額の施設に選択肢が狭められたわけで、義母の貯金を考えると、経済的な不安も大きかったわけです。
それと、「なんで老人施しい条件の施設を、短期間で見つけることができるか。
一刻の余裕もない、という思いで、行動に移しました。
介護はいつやってくるかわからない。
ゆえに、介護施設の情報収集は、常日頃から。
そうつくづく思います。
万一、妻か私がいきなり要介護3以上になれば、即、特養への入所のために今までの経験を活かすことができると思っています。
要介護3に満たない要介護度・要支援度の場合は、在宅介護・自宅介護を自動的に選択することになるでしょう。
次回は、
「介護施設検索から資料取り寄せと見学体験」というテーマでの回想になります。