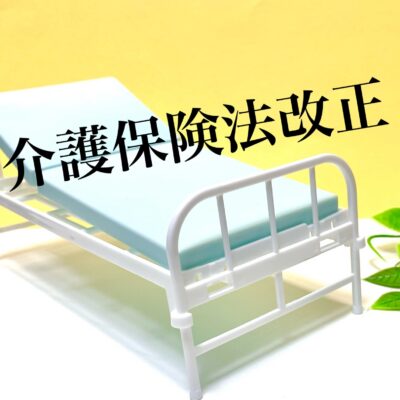93歳義母「サ高住」介護体験記|2015年の記録と気づき
2.地域包括ケア、急性期病棟・回復期病棟を知る|医療・介護の連携の仕組み
老々介護を考え始めるきっかけになった義母の脚骨折による入院について振り返った前回。
次に、入院・手術を経て、リハビリのための回復期病院への転院までの体験を回想します。
地域包括ケア、地域連携診療という仕組みを知る(2015/2/22)
義母が大腿骨頸部骨折で入院し、12日後に行った手術は無事に終了。
術後のリハビリでの転院先は、入院時に義母自身が希望した病院で、年末・年始に掛かることから、年始明けに。
地域包括ケア体制と急性期病棟・地域包括ケア病棟の役割
緊急で入院し手術をした公立病院が「急性期病棟」。
転院して、リハビリや在宅復帰支援のための回復期治療・サービスを行うのが「地域包括ケア病棟」。
その流れの中で、自宅介護や介護施設などをどのように行うかを行政や病院・介護施設などと相談。
そして検討していくプロセスとその業務活動を、包含して「地域包括ケア」と呼びます。
実は、義母が入院時に、病院サイドと以下の「大腿骨頚部骨折地域連携診療計画」についてサインしていました。
1.急性期医療としての<手術>病院
2.回復期医療としての<リハビリテーション>病院
3.維持期医療としての<かかりつけ>病院
「大腿骨頚部骨折地域連携診療計画」
それが分かるのが、次の<大腿骨頚部骨折地域連携診療計画>です。

規模の大きい公立病院や総合病院は、基本的には救急医療と手術を要する重篤な怪我・病気医療を主に担う。
そのため、通常の外来初診者からは高い初診料を取り、原則、一般病院からの紹介状を必要とする。
そういう規定は知っていましたが、実際にこうした「地域包括ケア」体制の経験は初めてでした。
それはそれで当然で、「地域包括ケア病棟」という仕組みは、昨年2014年4月に国が新設。このことは、この年2015年1月29日付の日本経済新聞夕刊で知りました。
医療機関の分業体制化を促進する政策。
利用サイドからすると、技術・経験・設備や、医師・看護師などへの安心感から、まずは大病院にと願うのは当然のこと。
ただ最近の動きとして、人間ドックを、そこそこの内容で総合的健康診断サービスを行う中堅規模の病院が総合化しつつ増えてきている。それはそれで、望ましい方向に進んでいるように思えます。
病院による介護サービス・介護施設事業経営への進出が加速化!
その総合化として、リハビリから介護サービスにつなげ、病院による介護施設・介護サービス事業化が一気に進んできている。
これも納得がいくこと言えましょうか。
その実態・状況などを、高齢者医療や介護保険に関する諸手続き等と共にその後経験することになりました。
(以上2015年2月22日、記)

----------------------------
医療・介護の密接な関係|社会保障費問題と地域住民のための地域包括ケア
医療と介護は切っても切れない関係です。
現在は、そのサービス業務連携問題よりも、双方において年々膨大に増え続ける社会保障費財政・財源問題との関係で問題視され、議論されることが多いですね。
どちらも超高齢化社会において財政負担の増大は避けられないこと。
一般的な議論・意見としては、国庫からの支出増は、こちらも増え続ける財政赤字を盾に極力避けたいところ。
(私は異なる意見を持っていますが、それは別の機会に。)
となると受益者負担と称して介護保険料の引き上げや窓口での医療費負担の引き上げがまず高齢者自身の負担増に跳ね返る。
当然それにとどまらず、現役世代の健康保険料、40歳以上の現役世代が負担する介護保険料の引き上げも同時に行われることに。
世代間の不公平性が常に問題になりっています。
急性期病棟と回復期病棟の連携も、実は、この社会保障費増大に歯止めをかける措置対策の一環という側面があります。
地域包括ケアは、病院間・医療機関間の連携にとどまらず、医療と介護の間の連携も含みます。
医療と介護の線引きも、病院と介護施設双方の間の実務レベルでの問題も微妙なところです。
しかし、利用する地域住民としては、1か所で医療受診、介護、支払いなどを済ますことができるに越したことはありません。
もちろん医療制度と介護制度という厳然とした違い・領域があるのでムリ。そのため、こうした関係・連携において「地域包括ケア」は絶対に必要で、かつ円滑に利用者のニーズに合ったサポートが行われることが望ましいわけです。
こうした利用者サイドの利便性と経営的利便性・効率性を考えて、病院が別法人で介護施設を経営する例が非常に多くなっている。
実は、後の体験記で述べる、義母が入所したサ高住も、隣接する医院が経営するものでした。
次回は、今回の地域包括ケアシステムに則っての
「リハビリテーション病院への転院により回復期医療へ」というテーマの回想です。