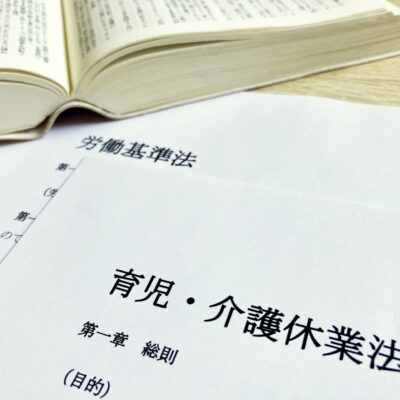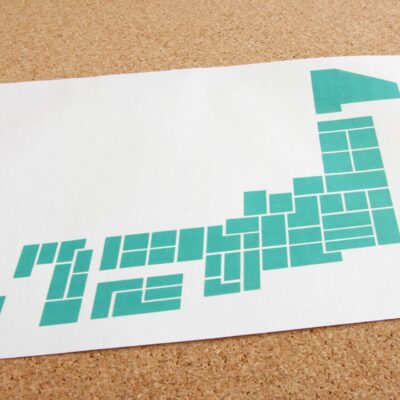「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズを終え、全体の総括を準備中です。
その前に「介護離職」という用語が入った手元にある2冊の書を、シリーズとの比較対比を兼ねて、補論として紹介することに。
前回、1冊目和氣美枝氏著『介護離職しない、させない』をまず取り上げました。
今回、もう1冊の樋口恵子著『その介護離職、おまちなさい』を紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なお、本稿は、一旦閉鎖した当サイトで2024年9月15日に公開した記事を、サイト再開に伴い、本日再掲したものです。
当時の実態と現状では異なる内容が含まれていることがあり得ます。ご了承ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本記事に、広告を挿入することがあります。

「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」シリーズー34:補論2
樋口恵子著『その介護離職、おまちなさい』から
初めに、同書の目次を参考までに以下掲載しました。
参考:【樋口恵子氏著『その介護離職、おまちなさい』(潮出版・2017年10月20日刊)目次】
プロローグ <ながら>介護、<トモニ>介護のすすめ
・20世紀に起こった寿命革命
・長寿社会に向けて変わらなくては
・介護する人も、される人も自由と尊厳を
・介護離職4つの大罪
・<ながら>介護のすすめ方
・企業も自治体も変わって、<トモニ>介護の時代へ
(コラム:<ながら>介護のための10原則)
第1章 働く人の<ながら>介護
CASE:夫婦共働き家庭の<ながら>介護
介護の旗を高々と介護される人の希望は?、遠距離介護も選択肢に、
介護嫁は絶滅危惧種、仕事と介護の両立に声をあげよう
CASE:おひとりさま女性の<ながら>介護
独立系職種の人のライフプラン、専業主婦と独立系の職種女性の年金比較、
まずは介護認定を、見守ることの大切さ
(コラム:女子アナ・町亜聖さんの10年<ながら>介護)
第2章 生活・尊厳重視の<ながら>介護
CASE:経済的に恵まれない人の<ながら>介護
地域の福祉事務所で相談、家族の概念を拡げる、孫の気持ちにも注意
(コラム:介護で困ったときの駆け込み先を知ろう)
CASE:孫に伝える<ながら>介護
ヤングケアラーという問題、人生の輝く時のアルバムを持つ、介護予防に取り組む
(コラム:すべての世代のための社会を目指してー高齢者のための5原則)
CASE:専業主婦の<ながら>介護
介護サービスを十分利用する、介護うつからの脱出
(コラム:介護うつに負けないために)
第3章 定年後の<ながら>介護
CASE:夫が妻を看る<ながら>介護
食事の自立を目指す、<ばっかり>人生を見直す、妻を介護するのは夫かもしれない
(コラム:男子厨房に入る)
第4章 変わる家族の現実、介護も変える
・他世代への想像力をもって
・緊急ボタンが点滅する介護問題
・総長男長女時代がやってきた!
・大シングル時代に突入した
・介護シングルの増加
・女、三度のすべり台、最初は出産
・最後のすべり台は介護
・介護の仕切り直しへ動き出す
(コラム:ながら介護を受ける高齢者の覚悟)
第5章 職場が変わる、女が変わる 男が変わる
・女性活躍社会が働き方改革をうながす
・それは国際女性年から始まった
・介護の社会化 ー 介護保険制度始まる
・働き方が変われば介護が変わる
・女性の問題はいずれ男性にも及ぶ
・<トモニ>介護に、動き始めた企業たち
・企業の地域活動で、地域力をアップ
・「商助」という考え方
・全国のコミュニティカフェ
・相談力こそ解決への第一歩
・<トモニ>介護の支援団体はどんどん増えている
(コラム:「介護離職のない社会をめざす会」の活動)
エピローグ
介護離職がない社会を/問題あれば対策あり/50年単位で未来を見据える/
介護が変わる、企業が変わる/若い世代の福祉参加-ドイツの例/再就職窓口の設置/
身寄りのない人の成年後見/周死期学会のすすめ/他人同士も支え合う、新たな地域
おわりに
樋口恵子氏著『その介護離職、おまちなさい』は、介護離職を世代と経済の視点から考える書
1.『その介護離職、おまちなさい』の要約・要点
樋口恵子著『その介護離職、おまちなさい』は、長寿社会における介護の課題を取り上げ、介護が生活の一部となった現代社会において、介護離職を回避し、仕事と介護を両立させるための方法を提供しています。
もちろんそれらは、介護離職を避けるための具体的な方策を提案する内容です。
著者は、そのために、介護を抱える人々に対して「介護離職を急がないで」と呼びかけ、仕事を辞めずに介護をする「<ながら>介護」や「<トモニ>介護」を提案します。
そして、介護は個人の負担だけではなく、社会全体の問題であるとし、企業や自治体が変わる必要性を強調しています。
以下に、本書の要点を整理してみました。
1)「ながら介護」のすすめ
樋口氏は、介護離職を避けるために仕事と介護を両立させる「ながら介護」を提唱しています。
介護を理由にすぐに仕事を辞めるのではなく、職場に支援を求め、家族や地域の協力を得ながら生活と介護を両立させることが重要であると述べています。
2)介護離職のリスクと解決策
介護離職は個人や家族に経済的・心理的な負担をもたらすだけでなく、企業や社会全体にも大きな影響を与えます。
著者は、企業が介護支援制度を導入し、介護者が仕事を続けやすい環境を整えることが急務であると述べています。
3)事前準備とサポートネットワークの重要性
介護離職を防ぐためには、事前の情報収集や準備が欠かせません。
また、地域の福祉事務所や介護支援団体の活用、さらに家族や友人、地域のネットワークを築いておくことが大切です。介護は情報戦であり、適切なサポートを得るための準備が不可欠です。
4)介護者に与える成長の機会
著者は、介護が人生において重要な役割を果たし、介護を通じて介護者自身も成長すると述べています。
また、介護を前向きに捉え、仕事と両立することで、自分の人生の自由と尊厳を保つことができると強調しています。
この本は、介護離職を防ぐための具体的な知識や工夫を示し、介護者とその家族、そして企業や自治体が協力して取り組むべき課題を探求しています。
なお、本書のAmazonの掲載ページには
「老老介護」「認認介護」「介護うつ」など暗いイメージがつきまとう介護。
一億総介護時代を迎える日を間近に控えた今、介護する人も、される人も、自分の精神的な自由と尊厳を失わず、前向きに生きるための方法を考える。
というPR文が提示されていました。
また、本書そのもののの表紙の帯には、以下が書かれています。
「ながら介護」「トモニ介護」のすすめ
「老老介護」「認認介護」「介護うつ」「介護離職による経済危機」「介護者・要介護者の共倒れ」
「夫婦共働きの家族は?」「おひとりさまの世帯は?」「夫が妻を看取る場合は?」
押し寄せる介護の不安を解消!
次に、樋口氏のプロフィールを同書より転載しました。
(参考):【樋口恵子氏プロフィール】
1932年東京都生まれ。東京大学文学部美学美術史学科卒業。
時事通信社、学研、キヤノンを経て評論活動を行う。
東京家政大学名誉教授・女性未来研究所所長。
NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長。
厚労省社会保障審議会委員、男女共同参画審議会のメンバーなどを歴任。
著書に『大介護時代を生きる』『人生の終い方』『おひとりシニアのよろず人生相談』『サザエさんからいじわるばあさんへ』『介護 老いと向き合って』『祖母力』など多数。
なお、前回の和氣さんの書の記事では、Amazon掲載のカスタマーレビューを紹介しましたが、今回は省略しました。

2.介護離職四つの大罪:『その介護離職、おまちなさい』から
介護<ばっかり>人生は、「介護地獄」を生み出す。
介護をつくして看取った後には、まだ長い人生が待っている。
中年以降の再就職は難しく、経済的に恵まれなくなるのは、目に見えている。
そうしたことから「介護離職には四つの大罪」があると、以下の警鐘を鳴らしているのが本書です。
「介護離職四つの大罪」(要約)
1)男性の介護離職が、今後大量に「貧乏じいさん」を生み出すことに
2)40から50代の会社にとって働き盛りの課長世代が介護を理由に辞める傾向が拡がる
会社にとって、それまでの人的投資が無駄になり大きな損失であり、本人にとっても、老後の年金が少なくなるなど、貧乏じいさんに直結する
3)国全体にとっても、個人所得税や社会保険料を最も多く負担しているこの世代の離職は、税収や社会保障費が減少し、困難が
4)中年世代の介護離職は、その下の世代にも影響を与える。家計が困難になり、孫世代の進学が困難になり、ヤングケアラーが生まれるなど、進学や就職を犠牲にする若い世代に連鎖する
個人的な感想を述べるとすれば、そういう側面も確かにありますが、介護を担う家族や個人の生活・人生への影響や、介護保険制度自体の問題と関連させての罪には触れられていないことに物足りなさ、偏りを感じています。

3.『その介護離職、おまちなさい』と「介護離職しないための8ステップ+1と実践法」の違いと活かし方
『その介護離職、おまちなさい』と当シリーズの違いを確認し、活かし方を合わせて考えてみることにします。
『その介護離職、おまちなさい』構成
プロローグ <ながら>介護、<トモニ>介護のすすめ
第1章 働く人の<ながら>介護
CASE:夫婦共働き家庭の<ながら>介護
CASE:おひとりさま女性の<ながら>介護
第2章 生活・尊厳重視の<ながら>介護
CASE:経済的に恵まれない人の<ながら>介護
CASE:孫に伝える<ながら>介護
CASE:専業主婦の<ながら>介護
第3章 定年後の<ながら>介護
CASE:夫が妻を看る<ながら>介護
第4章 変わる家族の現実、介護も変える
第5章 職場が変わる、女が変わる 男が変わる
エピローグ
おわりに
1)『その介護離職、おまちなさい』の特徴と『介護離職しないための8ステップ+1と実践法』との違い
本書と当シリーズとの違いははっきりしています。
実際に多くの高齢者の方々やグループと接点を持って活動してきている樋口さん。本書が「ながら介護」のさまざまなCASE、事例で構成されていることが最大の特徴です。
一方、本シリーズは、介護事例はほとんどないに等しく、関連する法律や制度、介護事業者や自治体・地域、企業など一方の当事者に関する記述が圧倒的に多くを占めています。
こうした介護に関する基本的な知識や情報収集、手続き・具体的な内容などについて、事前に知り、調べることが、介護離職をとどまらせることに非常に役に立つと考えているためです。
それらはまた、実際に介護する状況になった場合にも実務・実践的に有効です。
この内容は、前回の和氣美枝氏著『介護離職しない、させない』を紹介した記事で記したものと同じです。
言い換えれば、基礎知識編として、本シリーズ『介護離職しないための8ステップ+1と実践法』をお読みいただき、事例編として『その介護離職、おまちなさい』を利用頂くことをお薦めしたいと思います。
なお、私の義母の介護および終活体験記を、当サイトの初めに配置しています。
こちらで確認頂ければと思います。
⇒ 93歳義母「サ高住」介護体験記|2015年の記録と気づき – 介護終活.com
⇒ 98歳義母「特養」介護体験記|コロナ禍の特養介護生活と2介護施設での費用を11記事で回想 – 介護終活.com
⇒ 100歳義母 看取りと見送りの記録|終活を実践した家族の体験全10話(2022年7月〜10月) – 介護終活.com
2)樋口恵子氏提唱「<ながら>介護のための10原則」
「ながら介護」を提唱している樋口さんですが、本書の中で「ながら介護とは?」という問いに簡潔に答えている箇所が実は見当たりません。
ああ、こういうことを言うんだろうな、という想像で考えてみると、
・介護介護に集中するばかり、余裕がなくなり、心身の健康が害されることがないよう、他の何かをやりながら介護を行う
・なんでも自分が、と抱え込まずに、他の協力を得ながら、介護を行う
・(当然ですが)介護離職することなく、仕事も続けながら、介護も行い、仕事と介護を両立させる
・いろいろな悩みや問題・課題や事情を抱えながらも、工夫し、改善しながら、やりこなしながら、介護も行う
他にも考えることができると思いますが、そんな「ながら介護」をお薦めするといったところでしょうか。
その実践のために樋口さんが提唱するのが、以下の「<ながら>介護のための10原則」です。
「<ながら>介護のための10原則」
1.人生は長い。他にいろんなことをしながら家族を看よう
2.仕事を続ける。その覚悟をアピールする
3.決して隠さない
4.介護は情報戦と知る
5.ひとりで抱え込まない
6.事前準備を怠らない
7.地域の人間関係を大切に
8.「食べる」ための技術と手続きを手に入れる
9.「ケアされ上手」も年甲斐のうち
10.制度を上手に手に入れる
うっかりしていましたが、10原則の一番初めに書いてありました。
「他にいろんなことをしながら家族を看よう」というものでした。
また、プロローグにある「<ながら介護>のすすめ方」の項に入る前にこう書いてありました。
「仕事をし<ながら>、家事や生活を楽しみ<ながら>、人々とつきあい<ながら>、介護に取り組んでいく、そんなあり方を目指しましょう」
ずばり、これです。
3)『その介護離職、おまちなさい』の活かし方
・介護、終活、おひとり様関連書を執筆
このシリーズを手掛けた当サイトの名称は、現在、介護終活.com としていますが、開設時には、みんなの介護終活おひとり様.com としていました。
介護は、すべての人が体験するライフステージであり、そのために終活も必要であり、いずれおひとり様生活を送ることになる人が大半である。
それぞれのステージでの望ましい在り方、対応の仕方を考え、実践する。
そのために有効な提案や考察を行っていこう、という思いからのことです。
その思いは当然今も持っており、この名称に戻ることも考えています。
東京都知事選の立候補経験もお持ちの本書の著者樋口さんは、長く社会福祉・社会保障に関する政策提言や現実的活動に身を置いてきた大ベテランの方。
介護に関する著書、終活に関する書、おひとり様の書と大先輩ならではの著作活動を継続して行っており、本書以外にも数冊その著書を持っています。
ですので、この介護書だけでなく、一連の書もぜひお読み頂けたらと思っています。
・「ながら介護」CASEで読む、さまざまな家族・家庭状況、ライフステージ・ライフスタイルに応じた介護
介護や終活、おひとり様など高齢化社会の継続する課題について多くの人々との接点を持ってきている樋口さん。
その経験のほんの一端ですが、本書の構成を見れば即分かるように、「ながら介護」の事例を主に紹介することで読みやすく、より介護を身近に感じることができます。
ですから、身近に感じるだけでとどまるのではなく、それらを参考にして、お一人お一人の事情・状況に応じた、あるいは想定される介護に備えて頂くことに結びつけて頂きたいと思います。
・「トモニ介護」は介護の社会化と同義
「ながら介護」と併せて提案している「トモニ介護」については、プロローグの中の「企業も自治体も変わって、<トモニ>介護の時代へ」にある、この一文で理解頂けると思います。
「100年ライフを希望のあるものにするため、国や自治体、企業を含めて、介護者を孤立させず、<トモニ>介護を考えていこうという時代の入口に私たちは立っています。」
介護を担うのが個人、個別家族だけにとってのものでなく、国・自治体・地域・企業等形成する社会全体で担うべき課題と認識し、制度の充実、運営の柔軟性などを形成していくべきことを提案しているわけです。
・他にも役立つ情報満載
事例紹介の書と言いましたが、実は介護の実務書・基礎知識書的性格も併せ持っています。
「老老介護」「認認介護」「遠距離介護」「ヤングケアラー」「介護うつ」などの問題も扱っていますし、介護保険制度や地域組織、介護サービスなどについても具体的に記述しており、充実した内容の書とお薦めできます。
是非ご一読頂ければと思います。
※ 前の記事に戻ります:
※ 次の記事に進みます: